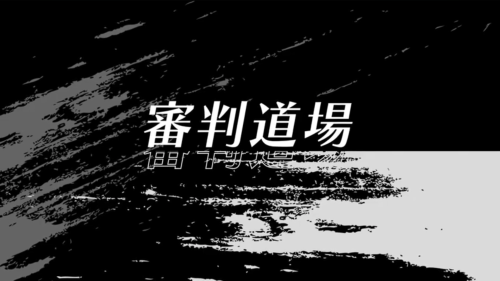ブログ
全日本空手道連盟 審判道場 中級編
こんにちは!
初級編では、審判の役割や権限についての講義でしたが、中級編は主に得点の正しい見極め、より詳細なウォーニング・ペナルティを学びます。
まず得点。
副審が旗を挙げる判断基準は下記の6項目。
1・良い姿勢
2・スポーツマンらしい態度
3・気力
4・残心
5・適切なタイミング
6・正確な距離
簡単に説明すると、
1・良いフォームのこと。バランスの悪い姿勢で出された技は有効技とはなりません。
2・相手にケガをさせようと大振りで攻撃を仕掛ける等の行為はダメ。
3・これには「スピード」「パワー」も含まれます。その技自体に気力が伴っていないといけません。
4・技を出した後も相手を意識し続けている状態。(技を出したあと背を向けたり、倒れたりしないこと)
5・適切なタイミングで出された技かの見極めが必要です。
6・技が有効になる距離のこと。旗が挙がらないパターンとしては詰まった技・抜けた技なんかがそうです。
次にウォーニングとペナルティについては、小学生の大会向けではありませんので割愛します。
軽微なコンタクトか重度のコンタクトで得点か反則かに分かれる説明でした。
接触によって相手の勝利の可能性を減少させた場合、ダイレクトに「反則注意」する必要があります。
この場合、ドクターとしっかり会話し継続可能かどうか判断しなくてはいけません。
ただしドクターが「継続不可」と判断しても主審が「継続可能」と判断した場合、主審はドクターの判断を覆すことが出来ます。
他には「掴みからの投げ」に関して、技として認められるケースと反則を取らないといけないケースがたくさん紹介されていました。
最後に試合映像を使っての得点 or 反則のケーススタディです。
自分が主審になったつもりで映像を何度でも観ますが、本番は一瞬の出来事ばかりですのでそれはもう大変です。
お題目は、主審はなぜ「やめっ!」をかけたでしょうか?
複数映像が流れてイージーなのもあれば、とにかく技が速すぎて判断が難しいケースもあります。
イレギュラーな事象が起こった時にも冷静に対処出来るよう、大会映像を審判視点で観ていかなくてはいけないと改めて感じました。
大会の規模と数に対して、審判をしてくださる先生の数が合っていないのが実情で、副審2人制も強化・活用されていきます。
大会では生徒の試合をスタンドで観戦したい気持ちが強いですが、微力ながら私も審判で貢献していかなアカンなと思う次第であります。