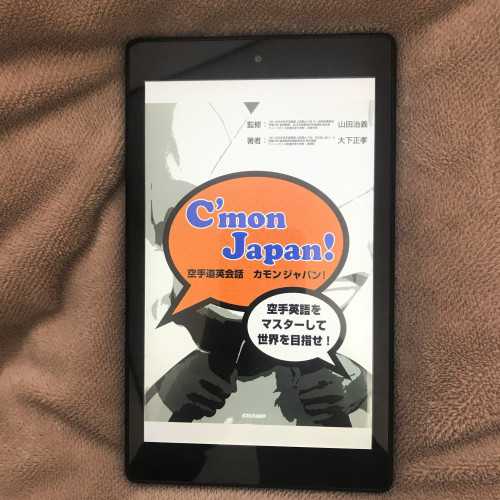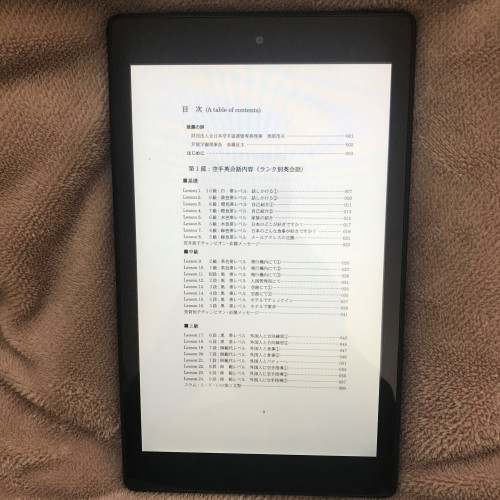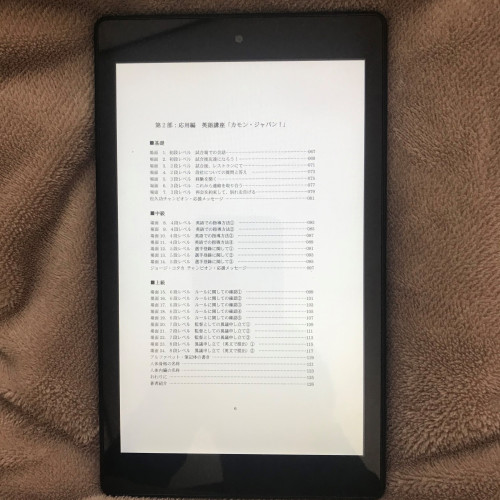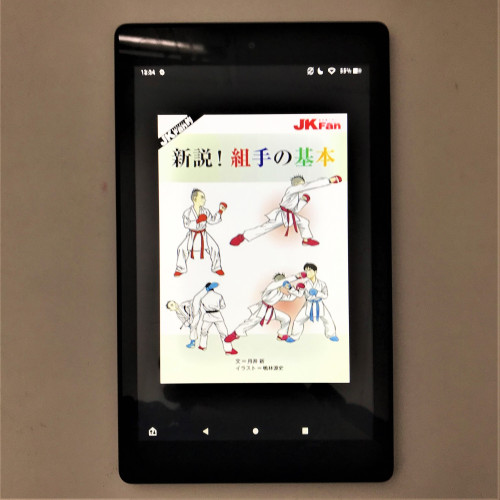ブログ
C‘mon Japan! -空手道英会話 カモン ジャパン!-
いつもありがとうございます!
外国籍の方とコミュニケーションを取る機会がある訳ではありませんが、以前から何となく気になっていた書籍です。
特に今読んでいる本もない事からポチッといきました。
内容の方ですが、人体部位の名称や手技なんかをサラッと知ることが出来そうです。
例えば『礼』ですと、Bow(バウ)
座礼はKneeling bow(ニーリング バウ)
立ち方では『平行立ち』を、Parallel stance(パラレル スタンス)
急所ですと『鳩尾』を、Solar plexus(ソーラープラクシス)
『手刀受け』では、Knife-hand block(ナイフハンド ブロック)
『逆突き』は、Reverse punch(リバース パンチ)
会話は無理でも単語くらいは覚えれそうなので、通勤のお供に丁度良さげです。
タブレットの中身が空手だらけになってきました。
新設! 組手の基本【ヒントはいっぱい! 予測の基本】
こんにちは!
Vol.11はヒントはいっぱい! 予測の基本 (2020年6月号)
最終回は攻撃の予測について。
対戦相手のデータがゼロに等しく、タイプが全く分からない場合、とりあえずこちらから仕掛けてみます。
しかし、ただやみくもに攻めるのではなく、データ収集が目的なので、まずは相手の反応を探る事が重要です。
深く攻撃してカウンターをもらわないように注意します。
①相手の反応を見る
まず、相手のタイプは主に自分から攻撃してポイントを取るタイプか、カウンターで取るタイプか。さらに、刻み突き・逆突き・蹴り等どの技がとっさに出るか、相手の傾向を探ります。人間の反応は本能的に体幹の動きに反応しています。つまり、手足を動かしてもあまり効果はありません。
体幹を動かしさえすれば、防御を空けることなく相手の反応を見ることが出来ます。
【刻み突きを出した時の反応】
自分の前拳側の肩だけを前に出せば、自分が刻み突きを出した時の相手の反応が読めます。
腕の構えは動かさず肩だけを素早く前に出すと、
(1)相手がそのままバックステップするか、
(2)中段に潜ろうとするか、
(3)突きを叩き落として刻み突きのカウンターを狙うか
(4)蹴りのカウンターをしてくるか
ある程度分かってきます。
【逆突きを出した時の反応】
自分の後ろの拳側の肩だけを前に出せば、自分が逆突きを出した時の相手の反応が読めます。
上段を出した時の反応は肩を相手の顔にぶつけるように、
中段は相手の腹部に肩をぶつけるようにすると、そこを突いた時の相手の反応を探ることが出来ます。
【蹴った時の反応】
足を掻い込んだ時に、骨盤を相手にぶつけるように、押し出すと反応を探ることが出来ます。カウンターを十分に注意して、蹴る側の腰を素早く押し出します。
②反応に対する対処法
軽く仕掛けて、相手の傾向を把握した後は、その対処法を知る必要があります。
相手が刻み突きタイプか、逆突きタイプかで、構えも目線も変えないといけません。
【刻み突きタイプの対処法】
相手の全身を視野に入れながら、相手の前拳側の肩口を抑えるようなイメージで構えます。
肩口を抑える場合、相手の左肩には自分の右手、相手の右肩には自分の左手を使うようにします。
【逆突きタイプの対処法】
逆突きが得意なタイプの選手に対しては、相手の全身を視野に入れながら、相手の後ろの拳側の肩口を抑えるようなイメージで構えます。
【蹴りタイプの対処法】
蹴りが得意なタイプの選手に対しては、脇を空けずに、縦に構えます。
蹴れるスペースを作らないことが蹴りを防ぐ第一歩です。まずは防御を心がけます。
腰回りを常に視界に入れておくと、反応が早く対処が可能になります。
癖を見る
対戦相手の癖を盗むことも必要になってきますね。例を挙げると、
①刻み突きの時に、予め前拳を下げる
②上段逆突きの時に脇を空ける
③中段逆突きの時に目線が下がる
④蹴る時に構えを開く
⑤攻める前に身体に力が入る
⑥攻める前に顔の表情が変わる
相手の癖を観察出来れば、心に少しだけ余裕が持てそうな気がしますね。
あくまでも確率からの一般論ですが、相手の前拳が下がった時は刻み突きが多く、逆に前拳が上がった時は中段突きが来る確率が高いと思います。
競技の達人シリーズ(DVD)や、今回の組手の基本シリーズで日々進化する「競技空手の今」を学ぶことが出来ます。
どれも理にかなっていて、目から鱗が落ちる知識が沢山詰まっています。
新設! 組手の基本【先の攻撃力! ステルスパンチをマスターする!】
こんにちは!
Vol.10は先の攻撃力! ステルスパンチをマスターする (2020年1月号)
空手の技の中に分かっているけど、食らってしまうことは無いでしょうか。
その技が反応出来ないほど速いかというとそういう訳でもなく、、
今回月井先生が紹介する技は、「速い」ことではなく「気配を消す」ことにあります。
スピードにはいずれ目が慣れてきます。慣れてきますと、その技は通用しなくなりますが、気配を消すことが出来れば、慣れることはないので何度でも決まります。
それをステルスパンチと呼んでいます。
「確実に見えているのだが、その突きに反応が出来ない」
身体の使い方に相手が反応出来ない要素があるからこそ、分かっていても防ぐことが出来ません。
では反応出来ない要素とは何か。驚くことに、全て普段の練習で行っている基本の中に含まれています。普段、稽古で指摘されている点を注意して行えば、ステルスパンチに必要な要素を身につけることができ、容易にマスター出来ます。
まさに、「奥義は基本にあり」ですね。
①力感がない
いわゆる力みがあると簡単に反応出来ますが、力みの無い技は反応しにくい。ステルスパンチは、力を入れて突くのではなく、力を抜いて突きます。
特に、技のおこり(始動)の部分で、力感を無くすことが重要です。
②手から先に突きを出す
この突きは、足から始動するのではなく手から始動します。
手が先に始動して、身体が手についてくる感覚です。力感も無くなり、脇が開くことも無くなります。
人間は、肩口が動いた時に本能的に反応します。力が入っていると突きは肩から始動してしまいます。
③ステップを省略する
通常の突きは、前足を踏み込んで突く場合が多いですが、ステルスパンチは前足から踏み込むことをしません。
感覚的には、その場から後ろ足を寄せて突く感じです。よって、ドンっ!と前足で強く踏み込みません。
気配を消す術の会得法
①正しい姿勢
正しい姿勢は力みを取り、反応を早め、全身を使って技を出すことが出来ます。
正しい姿勢とは、適度に下半身が沈み、上体は下半身に乗り肩の力が抜けリラックスしながら、視線は左右平行に相手を観ている状態です。
下半身を低くするのは、ドッシリと構えることが目的ではなく速く反応し動くためです。
正しい姿勢で立つと、全身の力は抜けているのに、腹圧が自然にかかります。立った瞬間に、肩と膝の力が抜けていて、腹には適度に圧がかかった状態です。
②抜きで始動する
正しい姿勢で構えた状態から、股関節と膝、足首関節を瞬時に抜くことで突きの動作を始動させます。
瞬時に抜ければ力の溜めが無くなり、構えたところから余計な動作をせず、突きを始動出来ます。
③始動時に息を吸う
息を吸う事により、力みが消え余計な動作もなくなる。息を吸う事で腹圧をかけることができ、技のスピードと威力が増します。
④摘まむように突く
突きを確実に極めるには、突く感覚を持たないこと。突こうと思えば腕に力が入り、結果肩が上がり、脇が開き、スピードも落ちます。
目標とするところに、米粒がついているのを想像し、その米粒を摘まむように手を伸ばします。
摘まむイメージを持つことで、手から始動し肘と肩は手の後ろからついていく形になるので、結果的に肩は上がらず、脇も開きません。
ものを摘まむ行為は、肩口を動かさないので、突きの時にこれをイメージ出来れば、相手の反応を本能的に遅くすることが出来ます。
⑤後ろ足を寄せて、素早く足を継ぐ
後ろ足で床を蹴るのではなく、後ろ足を前方に寄せるが、その時に同時に突きます。
床を蹴らないことで気配が消えますので、相手にとって反応が難しくなります。
後ろ足と奥の手を同時に前方に出すようなタイミングを心がけます。
新設! 組手の基本【苦手な技を克服する】
こんにちは!
Vol.9は苦手な技を克服する (2019年5月号)
-リーチの差に負けないスピードと技を身につける-
自分より体格差に勝る相手と対戦する場合、どうやってポイントを奪おうか当然考えます。
いつもと同じ戦い方では、手足の長い大きい選手の方が理論上有利です。
そこで課題になるのが、「相手の技をくらわずに自分の技を極める工夫」です。
「スピード」と「技」に絞って説明されています。
リーチの差に負けないスピード
(1)腸腰筋を鍛える
スピードを上げる方法のひとつに筋力をつけることとあります。踏み込んだ時のストライドを伸ばすためのトレーニング方法です。
一歩の移動距離が伸びれば、リーチの差を埋める事が出来ます。ここではジャンプ系のトレーニングをお勧めされていて、脚力とともに腸腰筋も強化出来るメニューです。
腸腰筋とは、姿勢の保持や脚を上げるための筋肉です。
単にスピード強化だけに留まらず、美しい姿勢を保つのも、この腸腰筋が大きく影響します。
①低くしゃがむ
②両手を大きく振って、高く遠くまでジャンプする
③着地は音を立てず、連続して飛ぶ
(2)手を伸ばしてステップする
攻撃の時は、ストライドを伸ばすとともに、腕も最大限伸ばすことを心がけると、到達距離はさらに伸びます。イメージは落ちて来たものをキャッチする感じです。
①組手構えで立つ
②前方に飛ぶ時に、手を伸ばす
③組手構えに戻る(上体をまっすぐに戻し、後ろ足を寄せる)
これを連続で繰り返します。
攻防の中で華のあるカウンター。相手は攻撃を仕掛けている最中ですから、防御の意識は欠如していますのできれいに極まる確率が高いといえます。
カウンターは大きく分けて2種類。
相手の攻撃をかわして極める「後の先」と、相手の出会いに合わせる「先の先」。
(3)相手に攻撃させる
まずカウンターを狙う場合、
・攻撃させたいところを意図的に空ける
・相手の攻撃の間合いに入る
のように相手の攻撃を誘発させる必要があります。
【突きのカウンター】
通常の構えから、相手の間合いに入るまで間を詰め、その時身体を後傾させ、後ろ足にほとんどの体重を乗せ、前足は母指球だけを床に着けます。
頭部は前進せず足だけ前進させます。要するに足は射程圏内、頭はギリ射程圏外です。
相手の攻撃に合わせ、懐に入って「先の先」で、中段逆突き。
間を切って、「後の先」での刻み突き。間を切る時は足で後退せず、後傾した上体を起こすと、適切なタイミングで突くことが出来ます。
【蹴りのカウンター】
①通常の構えから上体を前傾させ、上段突きを誘発する
②相手が突くのに合わせ、上体を後ろに倒しながら蹴りのカウンターを極めます
③もしも相手が攻めてこない時は、上体を後ろに傾けるのを利用して後ろ足を前に継ぎ、蹴りを極めます
時代の流れとともに、目まぐるしく変化(進化)する組手競技。
今もなお世界中で最新の技術を研究し続ける月井理論。
残りあと2本ですが、この「新設! 組手の基本」と「競技の達人シリーズ」から多くの知識を得られます。
熟読をお勧めします。
新設! 組手の基本【30分で組手の不得意を克服する3つのステップ】
こんにちは!
Vol.8は30分で組手の不得意を克服する3つのステップ (2018年12月号)
中段逆突きが極まらない最も大きな要因は、
・届かない
・刻み突き等のカウンターを合わせられる
この2点を克服すれば、中段突きが極まる確率がUPします。
①自分の間合いを確認する
自分の距離、攻撃の間合いを知るには、相手の前拳を利用します。
自分の前拳を軽く伸ばして相手の前拳に触れることが出来る距離が、自分の間合いと言えます。
お互いに構えた距離では、隙を伺っています。ここから間を詰めて前拳を触りに行きます。
②手を引かず、手に身体を寄せる
相手の前拳に触れた手を、引き手を取ってしまうと身体が空いてしまいカウンターをもらいやすくなります。更には前進しようとするのに、身体の一部を引いてしまうと、前進の距離も短くなってしまいます。
だからといって、全く引かずにいても腰を切ることが出来なくなり技に勢いがなくなってしまいます。
引き手は手を引くのではなく、逆に前の手に身体を寄せるイメージを持ちます。
突く側の肩を目標にぶつけるようにすると、相手の突きが抜けて行き、上段突きを極められる確率が減ります。
③間を切って反撃を断つ
たとえ突きが極まっても相手に反撃を許してしまえば、まだ失点のリスクは残ります。突きを極めた後、確実に反撃を断つには引き手が重要です。
突きを極めた後すぐに脇まで拳を引くことで、再び相手に対し真横になり、自分の的を小さく出来ます。引き手を使って素早く後退し、相手の技が届かない間合いに身体を置くことが出来ます。
しっかり引き手を取れれば、引く力で前足を掻い込んで蹴りへのコンビネーションに繋げることも容易です。
引き手は相手の反撃を断つだけでなく、次の攻撃に移る時でも効果を発揮します。
【逆体相手】
逆体がやりにくいのは、「逆体に慣れていない」ことが最も大きな原因です。
構えが逆になると、技も間合いも別物になります。
・前拳が使いにくい
刻み突きの軌道上に相手の前拳があるので刻み突きに入りにくくなります。
・後ろの拳が遠い
逆体相手の時は、逆突きの距離は拳1ケ分遠くなってしまいます。
①肘を触って突く
スムーズに前足から前進し、肘に触れながら突きます。この時、相手の肘の外側を触るようにすると、押っつけながら入ることができ、相手は対応が出来にくくなる。
②股関節を外旋させる
踏み込む時に股関節を外旋させてつま先を外に向けます。前足がマットに着く前に突きが極まることが望ましいです。この突き方で距離が飛躍的に伸びます。
股関節を外旋させると、拳が勝手に飛んでいきますので、相手にとって通常の突きよりも反応が遅れます。
③腰を回さないで突く
腰を切って正面を向いて突くと、自分の身体が開いてしまいカウンターを合わされやすくなりますが、この突き方なら始動時から残心を取るまで、身体が正面を向くことがありません。
注意すべき点は、構えたところからまっすぐに突き、鉤突きのように肘を張って突かないことです。
松濤館流の山突きに似た、腰を回さない上段逆突きですね。
【蹴り技】
①軸足を外旋させ、つま先を後ろに向ける
身体を開かないための練習として、蹴る前に軸足のつま先を蹴りとは反対方向に向けます。
つま先が横を向いたまま蹴ると、身体が「く」の字に曲がるので注意が必要です。
自分から蹴る場合は、軸足を身体の中心に寄せるが、この時に足全体を寄せるのではなく、踵を素早く寄せる意識を持ちます。
②膝の掻い込み相手のガードを無効にする
掻い込みによって中段を防御し、相手の前腕を構えたガードの無効化を図ることが出来ます。
前足刻み蹴りの時に、相手の前腕に触れずに上段を蹴る事が可能になります。
③突きながら蹴る
後ろ足で蹴ってもカウンターをもらわない方法です。
足を掻い込むと同時に、同じ側の手を突きながら蹴る方法です。タイミングとしては、突きを若干先に出すようにして、突いた腕の下に自分の膝があるようにします。
注意点は、蹴った足は正面に下ろさず、相手の外に着地させることです。そこに位置取りすることで、相手の反撃を断つことが出来るからです。