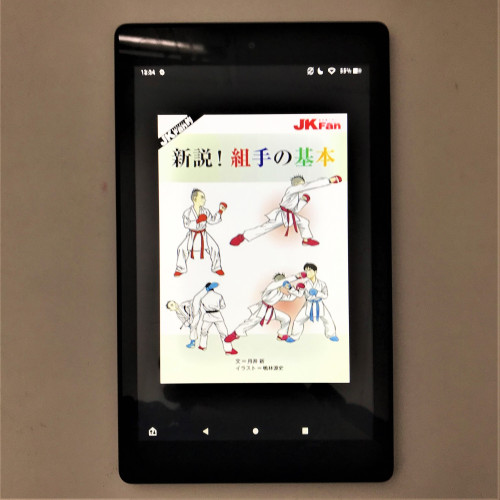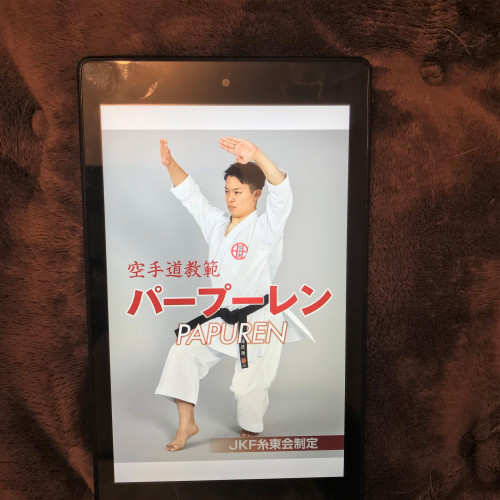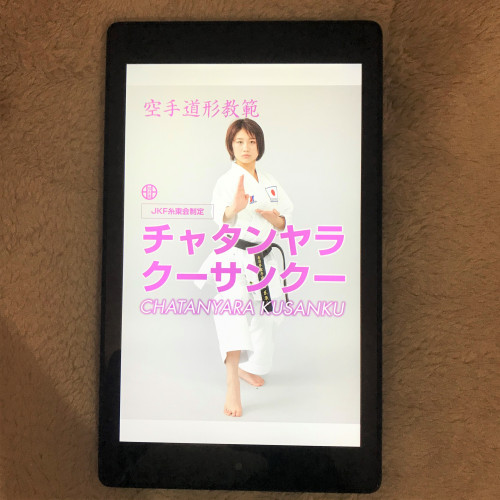ブログ
新設! 組手の基本【組手の基本・上級編】
こんにちは!
Vol.3は組手の基本・上級編 (2015年9月号)
これも、カニ構えについてです。
カニ構えは、やや浅めの四股立ちで構えますが、どれだけ強いかを説明されています。特に非力・軽量の人は四股立ち以外考えられないとまで言われています。
立ち方の違いによる強度の差を検証します。パートナーに両手を前に出して掌を重ねてもらい、自分が片手で押してみます。
押す際、3つの立ち方を試してみます。
検証1 押してみる
①:前屈立ち、または基立ち
①はパートナーが両手で構えていれば、よほどの力の差がない限り押すことは出来ません。この場合、単純に力対力の勝負です。
②:両足を平行に取る
②は相手に対して全く押すことが出来ないはずです。
③:四股立ち
③は力を入れて押さなくても、両足の膝裏を抜くだけで楽に押すことが出来るはずです。
検証2 片足で立ち、安定感を試す
④:軸足を十分に開かず、つま先を真横に向けて膝を掻い込む
④はパートナーに肩を押してもらってみると、簡単に飛ばされるはずです。
⑤:軸足のつま先を真後ろに向けて膝を掻い込む
⑤他の構え方なら、軸足を旋回させますが、カニ構えではスムーズに持ってこれますね。
次に動きやすさについてです。
カニ構えの場合、動きそのものが速く多彩になるだけでなく、技のバリエーションも増えてきます。カニ構えで得られるメリットを挙げてみます。
⑥細かな運足と安定
足を平行に揃える場合とつま先を外に開く場合では、運足が大きく異なります。
平行に揃えて真横に構えると、前進・後退は股関節が動き、足全体で行わなければならない。
つま先を外側に向けると、膝から下だけで前進・後退が出来ます。
膝から下だけで動ける分、身体の上下動が減り、目線が安定します。加えて、つま先を開けば、他の立ち方よりも急加速・急ブレーキ・急転換が可能となり、急激な方向転換でも体軸がブレずに安定して動くことが出来ます。
⑦スウェイとダッキングが容易
カニ構えは、他と比べて上半身を振りやすく、上体だけで相手の技を自在に避けることが可能です。また相手に正面を向く必要が無いので的も小さくなります。
特に、スウェイバック時カニ構えの優秀性が顕著に表れます。基立ちベースから上体を後ろに反らしても、振り幅が小さく十分に相手の攻撃をかわせないだけで無く、瞬時に基の姿勢に戻れません。これでは反撃に遅れてしまいます。
一方、カニ構えでは上体の振りが大きく楽に振る事が出来、万が一後ろに反った時に突き飛ばされても十分に耐える事が出来る位に強く、また反撃も容易です。
またダッキングに関しても、四股立ちのまま行えば瞬間的に身体の落下を利用し相手の攻撃を回避出来ます。
【刻み突き】
①:両つま先を開いてカニ構え
つま先を開くことで”おこり”が消え且つ遠くまで届く
②:後ろ足つま先を動かさずに前拳を構えた位置からそのまま突く
後ろ足で強く蹴らない分、力みが無く技の”おこり”も少なくなる
③:突いた手を思い切り引いて足をスイッチして残心を取る
まっすぐに突き込んでも僅かに線を外す事ができ且つ次の攻撃に移りやすい
留意点
①落ちてくるものを拾いにいくイメージで拳を出す
②突きが極まった瞬間の両膝の向きに注意する
③引きと同時に、両足を浮かせスイッチする
手が先に飛び → 上体が傾いて手に乗り → 足がついてくる 感じです。
【上段逆突き】ワンステップ
①両つま先を開く
②後ろ足つま先は後ろを向けたまま床を蹴って前進
③後ろ足股関節を内旋させて突く
【上段逆突き】ツーステップ
①両つま先を開く
②後ろ足つま先は、後ろを向けたまま床を蹴って前進
③前足が着地した瞬間に前足で床を蹴ってツーステップ目
④前進移動中に突きを極める
⑤両足が着地した時点では、突いた手を引いている
留意点
①前進時に構えを崩さない
②突く時に、前手を引かずに前手に全身が寄って行くイメージを持つ
③引き手を大きく取り、カニ構えで残心を取る
補足説明です。
前手を引かない理由ですが、前進して突く時に前の手を引いてしまうと、スペースが生まれカウンターを誘発するからです。
【蹴り】
①足が高く上がる
シーソーの原理で、片方を下げることでもう片方が上がる
②遠くまで蹴りが届く
首から下を振ることで、身体を遠くに飛ばして蹴る
③相手の突きが届かない
上体を倒すので、相手から自分の顔が遠くなる
屈んで蹴る
カニ構えでダッキングすることで反撃が容易になります。
①前足での裏回し蹴り
膝を掻い込んでさらに身体を倒して蹴る
②後ろ足での裏回し蹴り
後ろの肩を相手にぶつけるように腰を切り、後頭部を蹴る
③サソリ蹴り
前足が相手の外にある時は、後ろ足で蹴る
最後に、カニ構えで最も効果的と思われることは、角度・間合い・技の軌道が多彩になり、相手にとっては予想しにくいスタイルであり、気配を察知されない点だそうです。
気配を少しでも消すことが出来れば、相手の反応は僅かに遅れる分、自分の攻撃が極まりやすくなると言えます。
新設! 組手の基本【世界に見る組手】
こんにちは!
Vol.2は世界に見る組手 (2013年3月号)
カニ構えの続きです。ここでは、カニ構えから突けば20㎝距離を稼げると説明されています。
上体を真横にして、つま先を90度に開くと、顔の位置が10㎝ほど後方に移動します。
つまり両足の位置は同じでも、10㎝分だけ相手の突きが届かなくなり、逆突きをすれば自分の突きは10㎝伸びると言います。
つまり、構えを変えるだけで20㎝得と言うわけですね。
また、カニ構えは低リスクである理由にも触れています。
後ろ足つま先を斜め後ろに向けることで、相手の攻撃を最小限度に止められます。
攻撃を食らって最も危険な瞬間は、自分が攻撃を仕掛けた瞬間です。
相手に対し前進している時に攻撃を食らえば、ダメージは倍増します。
カニ構えでは、前足を踏み出しても後ろ足を壁としているために前足だけが、前進し、上体はその場に留まっていますので、カウンターのリスクが軽減されます。
刻み突きの時に、後ろ足つま先を前に向ける必要が無い理由を説明します。
斜め後ろにつま先を向けておけば、両足の裏全体が床に接地しているので、足裏全体で床を押す時間が長い分、結果的に床を押すエネルギーが大きくなるためです。
加えて、前足股関節の抜きや上半身の振り等、身体全体で前進することが出来る分、より速くより遠くを突くことが出来るという訳ですね。
新設! 組手の基本【カニ型組手】
こんにちは!
JKFanに2013年1月号から2020年6月号にかけて不定期で掲載された、月井 新先生の組手の基本を一冊に纏めた教範となります。
全11回に分けて紹介したいと思います。
Vol.1はカニ型組手 (2013年1月号)
ひと昔前の日本人選手の構え方が前提で話を進めます。
基本的には半身を取り、正中線を守ります。前足つま先は正面、後ろ足つま先は斜め前に向けています。
後ろ足のつま先が真横(あるいは斜め後ろ)に向いていると「崩されやすい」・「身体が流れている」・「後ろ足で床が蹴れない」と言った声が聞かれます。
それに対し海外選手では、相手に対して真横に構え前拳の後ろに自分の身体を隠し、基本的には両足のつま先は直角に開いています。
つまり、日本人選手は前屈立ちに近い構えに対し、海外選手は後屈立ち、もしくは四股立ちをベースにしています。
以下に相違点を挙げます。
1:上体の向き
日本人選手:正面に対し45~70°程 / 海外選手:90°に近い
2:両足つま先の角度
日本人選手:30~60°程度 / 海外選手:90°に近い
3:重心
日本人選手:やや前 / 海外選手:やや後ろ
半身の構えからの突きと、真横の構えからの突きを比較してみます。
半身の構えから基立ちで踏み込むと、前足と同時に身体全体が前進するため上体が相手に接近してしまう。
真横の構えからサイドステップで踏み込むと前足だけが相手に向かって飛び、身体を残すことが出来ます。そして、そこから腰を入れて突くので相手に取って射程圏外から突如突きが飛んでくる感覚となります。
相手のカウンターの射程圏外にいますので、刻み突きを食らう可能性が少なくなります。加えて、頭を後ろから押し込められるように入る事で、顔面が真っすぐに相手に向かっていくのではなく、線を外して突けるので二重に安全対策が取れます。
この突きで最も大切なところは、突く直前の立ち方にあります。
後ろ足のつま先が真横から斜め後ろを向いていれば、前足を飛ばしたときに身体は流れません。つまり後ろ足が「壁」になります。
これを、基立ちで構えると、前足を踏み込むと同時に身体全体が一緒に前進するので、身体が相手に早く近づくことになります。
カニ構えのフットワークのコツです。
・膝から下で動き、膝の位置は変えない
・逆突きは股関節の内旋で突き、突いた後は引き手と股関節の外旋を使い、素早く後退し距離を取る
・刻み突きに入る時も、両足を直角に開いたまま突いて良い。(後ろ足を開くことで線を外して入る効果がある)
・前足は踵から着地する
・刻み突きの後に間を切る時は、引き手と一緒に前足股関節を外旋させ、足をスイッチして後退する(次の反撃も素早くできる)
・両足のつま先を直角に保ったまま動き、必要に合わせて股関節の内外旋、肩甲骨の開閉を使って受け・突き・蹴りを行い、攻撃の後は間を切る
2022年現在の組手は、完全にカニ構えが定着していますね。
【糸東会】パープーレン
こんにちは!
チャタンとセットでポチっといきました。
買った瞬間読めるところが、タブレット版の利点ですね。
物覚えが悪く、長い形はずっと敬遠してきましたが稽古後に自由時間が有り余ってますので、挑戦しようと思い購入しましたが、、
中国福建省の白鶴拳に源流があると言われています。そのため、開手による攻防が特徴的です。
滑らかな動作の中に俊敏さも含んだ形です。女子選手向きな形ではないでしょうか。
初めて聞く立ち方、「座湾立ち」「添え足立ち」「鶴翼の構え」「酔羅漢の構え」なるものが出てきます。
打てるようになるには、相当時間がかかる気がします。
ごく一般的なパープーレンと思っていましたが、チャタン同様に糸東会が制定するパープーレン。大舞台で良く観るのとは、なかなかの違いでした。
【糸東会】チャタンヤラクーサンクー
こんにちは!
チャタンヤラクーサンクーは、「北谷屋良公相君」と書きます。
公相君と呼ばれていた中国の武術家が琉球を訪れ、その武術を北谷村の屋良親雲上という武人が習いました。
つまり、北谷(の)屋良(の)公相君が形名の由来です。
公相君の名がつく形には、「公相君大」「公相君小」「四方公相君」「知花公相君」など数種類の形がありますが、チャタンはこれらの形の原形と言われています。
タブレットで教範を購入し、じっくり目を通しましたが糸東会のチャタンは競技で見かける形とどこか違いがあります。
第1挙動で、上体をやや前方に倒し、両開手を上段にあげます。
第30挙動の脇構えでは、身体を斜めに向けています。
また、ジャンプの代わりに三日月蹴りなんかも。
特に後半は良く知るそれとは、まるで違う別形です。
皆が良く知るチャタンでも無く、古流チャタンでも無く、糸東会が制定したもう一つのチャタンでした。
模範演武は形も組手も、ハイレベルでこなす佐尾 瑠衣花選手です。