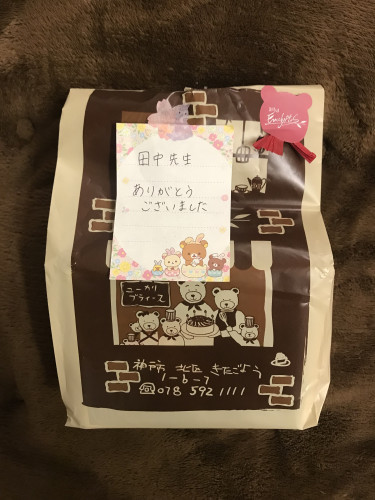ブログ
2024年4月28日(日)第1回谷派空手道心武館 段級審査会 @明石 勤労福祉会館
こんにちは!
道場生たちにとって待ちに待った審査会が勤労福祉会館で行われました。
午前中、三宮まで家族を送りそこから福祉会館に向かうことに。
普段使わない道で移動したのでホントにあってるのか不安でしたがナビのとおりに運転し無事到着。
なんと集合時間の1時間前に着いてしまいました。
イスに腰かけてゆっくり待っとこかと思ってましたら、なんと西明石の先生の姿が。
当日、館長から誰がどこを審査するか通達があります。
私は朝霧の先生と2審(オレンジ7級と青6級)でした。
イスに座り受付をしてますと、続々と道場生たちが。
さすがに審査中は写真撮る時間なんてありませんので、シャッターチャンスはこんな時くらいしかありません。
さて肝心の審査ですが、、
開始とともにチラッと朝霧の先生の顔を覗いてみると、どうぞ進めてください。
良い意味で進行は私のやり方に一任。
ははーん。
これは私自身の審査でもあると受け止めました。
いつの間にか、良くも悪くも開き直りが出来るようになった私です。
こうやって鍛えられて引き出しを増やしていくもんです。
崖に突き落とされた、子ライオンの心境です。
生徒だけではありません。
私も生涯学習というわけです。
いろんな指導方法がありますね。
基本・形・組手の順に審査は進みます。
道場生ですが緊張?してたのかな。
立ち方がうーん、、
道場ではもっと出来るのに。
基本は可もなく不可もなく
形の方は間違いこそありませんでしたが、打ち急いでしまったのかこれまでと比べ後退してしまった印象を受けました。
組手は積極的に技を出すことが出来ていましたので問題ありませんでした。
ただ、なによりも残念だったことが待機中のおしゃべり。
緊張感のかけらもなく、とても悲しい気持ちになりました。
グループ毎の審査が済むたびに、招集し一言ずつアドバイスを。
これは自分にとって非常に大事な時間でもあります。
同じ審査を観て朝霧の先生が感じたこと。
私が観た注意すべきポイント。
照らし合わせの作業でもあります。
中には激ウマな生徒もたくさん。
その子たちに対するアドバイスは目から鱗です。
とてもとてもとても上手いのですが、何かが違う。
その何かを生徒達に伝えていたり、審査後のちょっとした時間で身振り手振り私に教えてくださりました。
このアドバイスは大きかった。
自分の考え(道場での説明)より、ずっとシンプルで生徒にとって伝わりやすい表現かも知れません。
1審では白帯生たちが頑張っていたようです。
審査後に合流し、一人ひとりの表情を見ていると緊張から解放されたのか、とても清々しい顔をしていました。
この緊張感をいつまでも忘れず精進してくれることを願っています。
一般Eさん。
道場でもとても熱心に頑張っておられます。
後ろの方で拝見させてもらいましたが、とても素晴らしい形を打っていました。
道場でも生徒たちにとって、良いお手本となっています。
末永くよろしくお願いします。
おっと!
当道場から初めての飛び級が出現しました。
道場稽古では一切手を抜かず、超絶真面目にひたむきに頑張るKちゃん。
常に行動はテキパキで、
返事や気合は道場で一番デカく、
アドバイスを目で見てしっかり聞けて、
とにかく集中力の塊で、
隙間時間で教わったことを黙々と自主練出来て、
家練こなして、
自分に厳しく意識して稽古に取り組めるKちゃん。
ここまで空手に夢中になってくれてありがとうと言いたいです。
”ありがとう”
もっとたくさんの生徒を空手に夢中にさせることが私の役割です。
2024年3月24日(日) 第4回心武館特別練習会 (形) @中崎公会堂
こんにちは!
雨の中、中崎公会堂で4度目の特練がありました。
4月県大会と5月神戸市大会前の最後の特練です。
形オンリーの特練。
今日は道場の生徒が8名参加してくれました。
ゆりの一般生、Eさんも来てくれました。
進行スケジュールを西明石の先生が組んでくださいました。
数日前には資料をメール添付してくださっていたので、サクッと予定を確認して開始です。
今回私は茶帯グループの指定形。
いつものバンビ空手ではありませんでした。
常々ゆりの生徒以外のところが良いので、久々の色帯でした。
道場が少し狭く、進め方が難しかったこともあり結局、茶帯グループではなく緑帯グループに流れ着きました。
今回の私は柔軟体操当番を外れていました。
準備体操を終え、サーキットトレ。
まだまだ暖房も手放せない寒さですので、アップで身体を温めていないといけません。
私も生徒に混じってウォーミングアップです。
基本を白・オレンジ・青・緑・茶黒に分かれて行います。
この時まで私は茶黒あたりをうろちょろ。
メインの先生がおそらく自道場で行っている基本を持ち寄ってこられたのでしょう。
とても刺激を受けます。
普段とは異なる基本稽古。
基本は基本なので基本なんですがどこか新鮮さを感じます。
気になる点を修正しながら良い汗をかいていました。
ここから先、グループに分かれ形稽古です。
白オレンジのみ稽古するはずが、他の色帯の待ち時間が長くなることを懸念してか、青緑も真ん中あたりで稽古開始。
最終的には茶黒も場所を見つけて形稽古でした。
このあたりから予定が狂っていて、私はフラフラっと指導者の少ないグループに顔を出したり、、
ちょっとジプシーのようにうろちょろしてました。
流れ着いた先は緑帯グループ。
指導者一人で6人まとめてセイエンチンを担当されていました。
ちらっと茶帯に目をやると指導者が複数いることを確認。
そのまま緑帯に居座ることにしました。
何度か形を打ち終え、3人ずつ生徒を分け合うことに。
今思い返すと6人とも出身道場の生徒ではありませんか!
全員良く知る生徒です。
ある生徒はコロナ禍の前後に入会した生徒。
小学校に上がるか上がらへんかくらいだったかな?
お姉ちゃんにくっついてて凄く覚えています。
緑帯になるくらいまで頑張ってるんだと思うとなんか嬉しくなりますね。
ほかの生徒は金曜日顔を合わす生徒ばかりです。
金曜日も幼児や一般の指導に回ることが多いのでガッツリ稽古するのはホントに久しぶりかも知れません。
さてセイエンチン内容の方は、唯一無二の指定形。
基本は外すわけにはいけません。
ただ基本通りやっても競技では評価に結びつかないところが難しいところです。
・四股立ちのスピードの上げ方
・手技のスピードの上げ方
・四股立ちの極め方
・外し技の意味(分解)
・呼吸法
・手首のスナップ
・下半身の連動で手技を出す
・丹田の意識
・三戦立ちの締め
・波足移動
こんな感じだったかと。
少しでも競技力が増してくれることを祈るばかりです。
道場は離れても、縁があって出会った生徒たちです。
みんな素直で可愛い生徒です。
ゆりの生徒たちも、形を打ち終えたあとに個別に指導してもらえたりと得るものがあったかと思います。
いっぱい頑張って、良い汗かいて、もっともっと空手好きになってくれたら嬉しいな。
今日こんなことが。
私がお世話になっている道場生Cちゃんが退会されました。
会えばいつも笑顔で迎えてくれて、お世話好きで仲間想いの優しい女の子でした。
タイミングがなかなか合わず最後もお別れ出来ずでしたが、プレゼントを用意してくれていました。
元気でね!
帰りにもいろんな生徒からたくさんおやつもらった。
みんなありがとー!
2024年3月10日(日) 第3回心武館特別練習会 (組手) @中崎公会堂
こんにちは!
2024年度3度目の特練が中崎公会堂で開催されました。
この中崎公会堂、ゆり生にとって初めての場所。
私のお気に入りの場所です。
ここ最近使ってなかったのか、随分久しぶりに感じました。
明治時代の建物だと聞いていますので、築100年超えかと。
ただ空調整ってませんので、保護者の方は激さむだったのではないでしょうか。
道場生は1日組手でしたので大丈夫だったと思いますが。
稽古の方は今年から特練の進め方に大きくメスが入りました。
従来では形・組手どちらか好きな方に分かれて行っていましたが、今年度より県大会ベスト8クラスの選手を強化組、その他の生徒を育成組の2つ(計4つ)に分かれて稽古することになりました。
同じ組手でも強化と育成が同じメニューをこなすことはありません。
生徒個々のレベルに合わせた特練に生まれ変わりました。
この日のメニューはこんな感じでした。
1・準備体操
2・ウォーミングアップ
3・組手新ルール説明会
4・組手基本(帯分け)
5・組手稽古(グループ分け)
2024特練に申し込みしていたS君は欠席。
前回に引き続き、3年生S君と2年生R君が飛び込みで出席の計7名でした。
毎回飛び込み参加も歓迎していますので、どんどん稽古に参加してほしいです。
いつもと違う指導者、初めての場所、知らない他支部の生徒とともに稽古する緊張感を感じつつ自分を高めていってほしいな。
今年度特練の準備体操は私が担当しています。
主に肩甲骨と股関節まわりの可動域が広がるようなメニューを組んでいます。
肩甲骨回りは大きな突き技を出すためには大事な運動ですし、股関節まわりは蹴りです。
他にもハムスト伸ばすことでケガ予防にもなります。
前任の先生はラストに体幹トレ入れてたな。
ケガしたら空手どころではありません。
休んでる間、ライバル達は稽古を重ねますので差が広がる一方です。
ケガの予防はしておくようにね。(道場稽古の前にストレッチやっといてくれると嬉しい)
準備体操の次はアップ。
ここでしっかり身体を温めていないと、これまたケガに繋がります。
ジョグやダッシュ系にいろんなジャンプがあったり、組手フットワークなんかです。
アップで身体を温めた後いつもなら基本に入りますが、組手新ルールの説明でした。
いろんな生徒が居てますので、そもそものルールから。
・得点部位(突きの距離と蹴りの距離も)
・反則部位(種類も)
・先取(せんしゅ)とは
・あとしばらく(残り時間15秒)
・先取取り消し(反則注意)
・新ルール(C1とC2の統合)
・主審と副審の役割(主審:反則・副審:技)
・同点先取無しの場合の勝者の決まり方(技の難易度 → 副審判定 → 主審加わる)
・身だしなみ(主に女子選手)
20分間で上記の説明を生徒と保護者を交えて行いました。
保護者の方の中で、分からないことがあれば道場で聞きに来てください。
4月に入れば試合形式の中で生徒向けに、ルールについても触れていきます。
改めて感じますがこの新ルール、先取と蹴りの重要性が増します。
戦略上、蹴りを被弾しないガードの技術と逆に蹴りを最短距離で極める技を磨かなくてはいけません。
試合展開によっては、前に前に出てくる相手によってはカウンターの正面蹴りが有効になるかも知れませんね。
ひとつ気になるのは、主審や監査は赤青の極めた技を頭の中で覚えておくのは至難の業だと思います。
これをひと大会ずっと集中して出来るのかな。
記計係りがメモしとくんでしょうか、、
ここから帯ごとに分かれて組手の基本に入りました。
私は白帯(バンビ)のお手伝い。
構え方から始まりフットワーク、突き、蹴りを楽しみながら。
人口密度の高いオレンジ帯(と青帯)に行こうかとも思いましたが、振り向けば道場生がいっぱいいましたので止めました。
せっかくの特練だし、違う刺激を受けてほしいので止めときました。
引き続き、バンビ向けの指導が長けている西明石支部の先生のサポートに回りました。
組手の基本から、少し難しい内容に入りました。
組手のコンビネーション。
リズムの中から刻み突き → 中段突き → 刻み突き → 刻み蹴り → 上段逆突き
これを何度も繰り返しているうちに、段々リズム感が良くなり技が繋がってきました。
技が上手くだせた時の笑顔を見てると、どこの道場の生徒でも可愛く思えてきます。
名前も顔も一致しない生徒(ゴメン)ばかりですが、やけに人懐っこくて可愛かったです。
さてゆり生の頑張る姿もチラチラ見てました。
さすが特練に来る生徒達です。
皆良い顔して懸命に努力してました。
(でも打ち込みの時は礼をすることを忘れずにね)
それでこそ我が生徒!
突き技の基本
フットワーク
打ち込み
反応
こんな感じだったと思います。
次回は今月24日!
場所は今回と同じ中崎公会堂です。
形オンリーでやりますので、S君R君に続く生徒が出現することを期待します!
参加した生徒は皆、終わったあと達成感ある良い顔を見せてくれますので一度経験してみてほしいな!
2024年2月18日(日) 第2回心武館特別練習会 @垂水体育館
こんにちは!
空手3連チャン最終日は垂水体育館で特練でした。
道場からは6名エントリーしていますが本日は2名欠席。
登録していない生徒でも、当日飛び込み参加可能で2名来てくれました。
形3名:組手3名でした。
今日も形道着でしたが、ポカポカ陽気で途中インナー脱ぎたくなるくらいの熱気。
早めに着いたので数本形を打ってましたが、体育館の床が汗で滑りまくりでした。
ちょい苦手かな。
今年の館の特練方針「基本の見直し」
冒頭の挨拶で基本をキッチリ磨くことで形にも組手にも活きてくるとありました。
ホントにその通りで、立ち方が間違っている選手で入賞する人を見た覚えがないくらいです。
腰が高い・正しい長さ(幅)等です。
キレとかスピードとか極めとかは、基本がしっかり出来てからのお話です。
寝てても正確な立ち方や技が出せるように、徹底的に見直すことにしています。
帯ごとに分かれて行う基本を約1時間。
第1回目の反省を踏まえて、今日のメニューを組まれています。
私は白帯組の補助を。
幼児ばかりですが、並び順を前回と変えたのが良かったのかな。
他にも手を加えてますが、前回よりも実のある練習会になったんじゃないかな。
60分基本練習を集中出来ない生徒も居てましたが、何とか合格ラインには乗ったんじゃないかな。
参加するからには、少しでも上達してほしい想いは変わりませんので。
私の背中で、小学生白帯組とオレンジ帯が基本頑張ってました。
普段と違う先生指導の基、東西南北に向きを変えながら、あらゆる立ち方を極める練習なんかでした。
もうひとつ奥では青・緑帯グループ。
小休止の合間にチラホラ観るくらいしか出来ませんでしたが、正面蹴りの稽古だったかな。
どんな稽古してるのか、興味津々ですので動画中心で撮ってました。
いまだにHPに動画を貼りつける方法が分からないので、もっぱらINSTAです。
めっちゃ簡単なので便利です。
基本を終え、形・組手に分かれます。
私は形。
生徒一人ひとりの希望を聞いてると、いろんな種類の形に分かれましたので私は補助では無く、指導することに。
3年生と4年生の女の子2名でバッサイ大でした。
3年生の女の子とは本部道場で居残り稽古の時間、ちょいちょいバッサイ大やってるかな。
確か西明石の生徒だったような気がします。
ひと通り、形を見せてもらいながら、気になった部分を修正する感じで進めました。
順番を教えるくらいなら喜んで指導しますが、形は所属する道場の先生の特徴というか色みたいなのもありますので、どこまで踏み込んで良いのやら正直難しいです。
まあ割り切ってやりますけども。
結局道場で指導する身体の使い方を教えたり(重複することが多いので)、小さく引き手を使う方法だったり、腰の切り替えしなんかです。
蹴りの挙動がどうしても難しいようで股関節のつまりを取ったり、ハムスト伸ばす方法をなんかも織り交ぜながら、軸をブラさずに蹴るコツなんかを指導しました。
2人とも超真面目。
真剣に目を見てお話を聞いてくれるので、指導にも熱が入ります。
あっという間の1時間でした。
ちょこちょこ組手も見学してました。
間合いの計り方、刻み突きなんかだったかと。
次回の特練は3月10日!
場所は中崎公会堂です。(明石福祉会館のすぐ近所)
道場が狭いので全員で組手!
組手って怖いイメージがあって遠慮しがちだけど、
組手怖くないやん!
やってみると楽しいやん!
って思えるメニュー用意して指導者一同待っていますので、
今日の特練で2名飛び込み参加してくれたように、次回も道場生が来てくれることを期待しています。
春先には大会が続きますので、道場稽古やら特練やらで自信つけよう!
2024年1月28日(日) 第1回心武館特別練習会 @明石勤労福祉会館
こんにちは!
怒涛の空手5連チャン最終日は、2024年第1回目の特練でした。
自宅に戻って少し休憩して、覚えてるうちにこのブログを書いてますが、とにかく疲れた。
水曜日の夜練からですので疲労困憊です。
昨年から参加人数が2名増え6名となりましたが、いろんな理由で今日参加出来たのは2名でした。
形:1名 組手:1名
稽古開始前に指導者から一言挨拶がありました。
私からの挨拶は、感謝の気持ちを忘れずに持つこと。
特にゆりの生徒に向けたメッセージ。
休みの日に遥々遠いところまで連れて来てくれています。
ほんとなら家の近くの道場でも十分なのに、わざわざ1時間近くかけてです。
特練参加出来ることを決して当たり前とは思わず、両親に感謝しながら今日の稽古を頑張ってほしいと願いを込めた挨拶でした。
言葉の意味が理解出来た生徒は、これからの道場稽古でも簡単には手を抜けなくなるよ。
挨拶のあと、全員で記念撮影でした。
1・柔軟体操
2・ウォーミングアップ
3・固定式基本
4・形 or 組手
【柔軟体操】
全体で体育館をランニングし、柔軟体操でした。
今年から担当は私。
形も組手も肩甲骨と股関節の可動域が広い方が良いのでその辺を重点的に行いました。
どの程度時間をかけて良いのか手探りでしたので、用意していたのが全部やった訳ではありませんでした。
時々説明交えながらストレッチしてましたが、親指の向きひとつで肩甲骨が更に広がりますので聞き漏らさないようにね。
【ウォーミングアップ】
今年の特練は指導者参加型です。
生徒と同じメニューをこなしましたが、一発で汗かきましたね。
明石福祉会館は冷暖房設備が整ってません?ので身体の冷えを心配してましたが汗かきました。
でも入口の扉が開放しっぱなしでしたので、座って観ている保護者の方は寒かったことと思います。
ジョグ・ダッシュ・ジャンプ・腹筋・背筋・腕立て伏せ
あとなんだっけ。
とにかく汗かきました。
どこの道場でも白帯生可愛いですね!
【固定式基本】
ここからは帯毎に分かれました。
私は白帯の補助。
冒頭の挨拶でもありましたように、今年一年かけて、特練では基本の見直しを行います。
ゆりの2人はオレンジ帯でしたので私の後ろ側でした。
小休止の合間、チラチラ見てましたが練習に食らいついていました。
気迫のこもった表情で基本頑張ってた。
いつもと違う先生の指導、新鮮だったんじゃないかな。
さて、白帯の基本ですが幼児から1年生がズラリ。
仲の良い友達同士でしょうか、遊び半分の状態でした。
これがゆりだったらどうなっていたことか、、
一列に並んで基本していましたが、配置の見直しは必須です。
間に知らない生徒を挟んで稽古に集中させないといけないかな。
ピリッとした緊張感がほしい。
【形 or 組手】
私はオレンジ帯の平安五段でした。
10名オーバーでしたので指導者3人体制でした。
しまった。
自分で生徒の振り分けしましたが、ゆり生が入ってしまった。
普段とは違う指導を受けてほしい思いがあったのですが上手いこといきませんでした。
ごめんね。
指導内容は、どうしても普段の延長線上になります。
特練だからといって何か特別なことを教える訳でも無く、いつものように進みました。
今週から取り入れている、キレとスピードの上げ方を重点的に部分練習で指導しました。
今日の形で感じたことは、スピードとタイミング、あと腰のキレ。
まだまだ修正する部分は多いですが初挑戦の特練。
参加すると決めただけでも、ひとつ成長出来たはず。
いっぱい練習してもっともっと上達してほしいと思います。
形が小休止する合間に、後ろで組手を頑張るR君をチラ見。
組手の基本や打ち込みだったかな。
今回のような合同練習する場では、同学年の生徒がたくさん集まります。
形は自分と向き合いますが、組手は相手が居てこそ成り立ちます。
積極的に組手に挑戦して、場数を踏んでもらいたい思いが強くあります。
組手の中でも、強化と育成とでコースを分けていますので自分と、どっこいどっこいのはず。
経験重ねる毎に動きが良くなってきますので、貪欲に挑戦続けてほしいです。
特練申し込みしていない生徒でも、都度参加可能です。
もっと増えてくれれば嬉しいな。