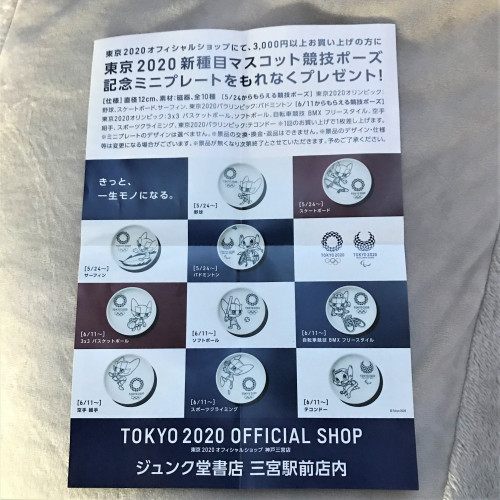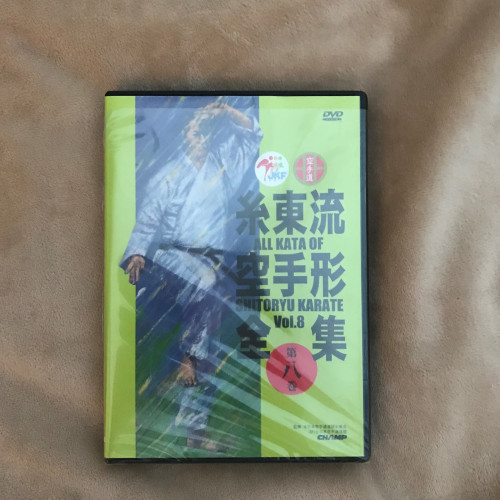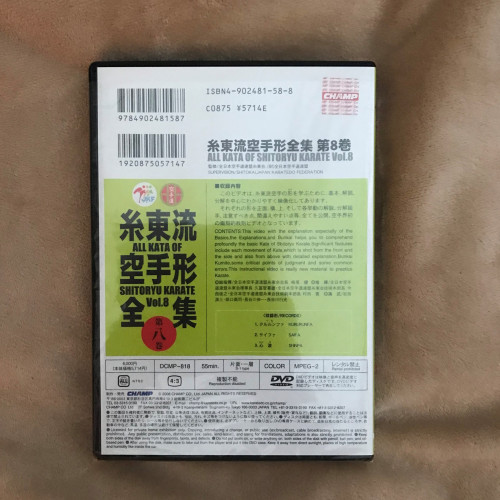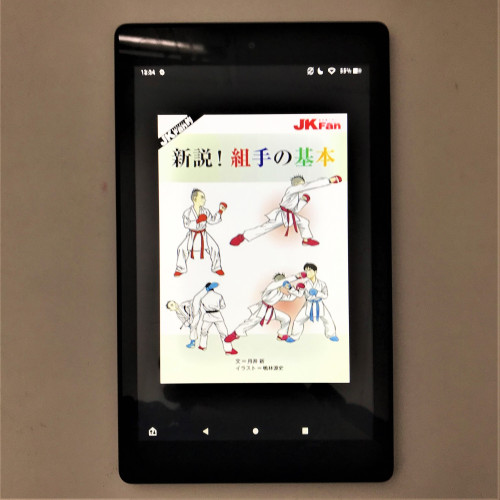ブログ
2022年7月24日(日) 第4回心武館特別練習会 @明石勤労福祉会館
こんにちは!
今日は明石福祉会館で4回目の選手育成講習会でしたが、13:30~15:30の2時間「スポーツ外傷と障害について」のテーマで座学でした。指導者はもちろんのこと、
今日稽古に来た生徒や父兄も参加です。
打撲したり捻挫したりすると患部は当然はれてしまいます。
はれる→冷やす→圧迫→心臓よりたかく上げる→安静にする
RICE処置ですね。
冷やす場合は、氷で10分~15分。腫れが強い時は1時間以上あけて2,3回繰り返します。
保冷剤は凍傷になるのでNG。
スポーツをしていると、膝が痛い・踵が痛い・足の裏が痛い等が起こり得ます。
障害の原因は、使い過ぎ・成長期・体が硬い・姿勢が悪い等が挙げられます。
運動をし過ぎると筋肉が硬くなりケガをしやすくなりますので、動いた後はストレッチやマッサージなどのケアが大切です。
次に、膝の障害に効果的なストレッチです。20秒を超えたあたりから効果が表れると説明がありました。
1・大腿四頭筋ストレッチ
・どちらか横向きに寝転がり、上側の足をお尻に付けるように伸ばします
・伸ばした状態で更に膝を背中側に引き付けます
2・腸腰筋ストレッチ
・どちらか一方の足を大きく前方に倒します
・一番伸びたところで慣れてくるのを待ち、そこから徐々に伸ばしていく
3・臀筋ストレッチ
・長座の状態から片膝を立てる
・片膝の上にもう一方の足を乗せる
・両腕で立てた膝をホールド
・そのまま後方に倒れる
4・ジャックナイフストレッチ
・閉足立ちの状態から踵が浮かないようにしゃがむ
・足首を持ったままお尻を上げる
・10回*3セット行う
限られた時間の中で、疲れた身体をケアする時間も必要ですね。
教わったことをゆり道場に持ち帰りたいと思います。
さて、残り1時間は形と組手に分かれて稽古です。
私は形グループの白帯組の指導補助です。
形は立ち方が非常に重要ですので、基本に30分使い残り30分を平安二段です。
白帯さんへの指導はもちろんですが、先生によって異なる、説明(表現)の仕方を勉強しています。
指導の引き出しを増やしていきたいと思っています。
2022年7月23日 (土)道場稽古16
こんにちは!
何を聞き間違えたのでしょうか。体育館に空調工事をすると聞いており、今日から冷房が効いた中で快適に稽古が出来ると思っていましたが、、
大きな勘違いだったようです。
暑くて倒れそうです。
さて本日のメニューです。
動(静)的ストレッチ 10分
固定式基本 15分
移動式基本 30分
組手基本 20分
形 40分
いつものように、座礼/黙想で心を落ち着かせます。が、、入り方をしくじりました。
前回の稽古がものすごく集中出来ていたので、振り返りをしてから稽古に入るべきでした。
グルっとランニングをしたあとストレッチ。ここはいつもと変わらず。
うつ伏せ(仰向け)ダッシュと反応のアジリティで、身体を起こします。
固定式基本はいつものように、突き・引き手・中段横受け・上段揚げ受け・下段払いです。
ひとつ受け技を増やそうと思っていましたが、どこか集中しきれていない感じがしましたので、今回は見送ることに。
移動式基本では、前回少しだけ触れた腰の入れ方を改めて説明。移動基本を通じて運足を学び、締めの感覚を掴みます。
ドンっ!と踏み込まず、足で雑巾がけするイメージで進み腰を入れます。
骨盤を自由に動かせるようになれば、逆腰を入れたりと自在に操れるようになり、その結果形競技でキレのある動きに繋がります。
次回から、骨盤操作に繋がるメニューを取り込みたいと思います。
次、組手基本です。
前回に引き続き、もう一度構え方の説明です。
構え方とフットワークが出来ないうちに、技の練習に入るとメチャクチャになってしまうので、丁寧に説明です。
今日のポイントは、
1・フットワークは「飛ぶ」のではなく「沈む」
ほんの少し浮かした踵を踏み込むイメージ。
飛んでる瞬間は無防備です。攻撃は出来ませんし、当然防御も出来ません。
2・前後移動する時「歩幅は変えない」
動かして良いのは足首だけ。足全体で移動すると、動きを察知され相手に反応されてしまいます。
構え方の説明中、「後ろの肩を前の肩で隠し相手に見せない」とサラッと触れたのですが、組手稽古が終わり休憩中に1年生の生徒が、
なぜ後ろの肩を見せてはいけないのか、質問にやって来ました。
分からないことを分からないままで終わらせないところに関心しましたね。とても嬉しかったです。
答えは、後ろの肩が見えてしまうと身体が開くので、自分の正中線を相手に晒してしまうからです。
最後は形です。
大会で打つ形を全体で数回あわせ、個人練習に移ります。体育館が広いので思いのまま稽古が出来ます。
その間、一人ずつ呼び出し短い時間ですがマンツーマン。
長所を褒め、修正点を伝えます。アドバイスをどれだけ理解/意識して一人で稽古出来るか。形稽古はこれに尽きます。
最後はまた全体で合わせて終了です。
・突きの位置は水月 肩の力を抜く
・歩幅は一定に保つ(長さと幅)
・おへそは進行方向に向ける
・目付は前(常に仮想の敵)
・力まず動きを滑らかに(力をこめるのは受け(突き)の瞬間だけ)
・転身(向きを変える際)中段横受けの準備をしながら
・拳(手首)を立てない
・技は引き手で極める
・発声は腹の底から
・形の始まりと終わりに礼は必ず
各人にかけたアドバイスです。
自宅で練習する時に、意識してもらったら必ず変わります。
東京オリンピック記念 公式グッズ
【糸東会】糸東流空手形全集 第8巻
こんにちは!
空手形全集 Vol.8です。収録形は、
1・十七(クルルンファ)
2・サイファ
3・心波
接近戦を想定したクルルンファは、投げ技・倒し技・逆技・羽交締めの外し等、様々な技術が集約された内容の濃い形です。
剛柔流のクルルンファは第1挙動は、押え受け/繰り受けで始まりますが、糸東流は手刀受けですね。
サイファもクルルンファ同様に剛柔流の指定形です。
単調な基本動作で構成されていますが、相手に手首や襟を捕まえられたり、足払いを外したりと護身術的技法が織り込まれた形と言えます。
心波は上地流の流れをくむ形で、繰り受けが特徴的です。
三戦立ちからの動きにリズム感が感じられます。接近戦からの蹴り技に工夫が必要です。
新設! 組手の基本【ゼロの間合いを制す】
こんにちは!
Vol.6はゼロの間合いを制す (2017年6月号)
※ゼロの間合いとは、相手と密着した状態を指します。この記事が掲載された2017年当時はまだ「分かれて」・「続けて」がありませんでしたので、それを承知の上でご覧ください。
密着したゼロの間合いの中で、何もせずに離れるか、審判の「やめ!」を待つのは非常にもったいないことです。
なぜならば、自分が間合いを詰める必要も無く、相手が目の前にいてくれるからです。ここで何もしないのと、攻撃して終わるのでは、その後の展開に大きな違いが生じてしまいます。
たとえ得点にならなくても、攻撃で終われば審判に積極性を印象付けることが出来ます。
ゼロの間合いから直接攻撃は出来ませんので、攻撃の前に自分の間合いを作り出す事が重要です。また接近していれば相手も攻撃できる状態だということを念頭に入れなければなりません。
①自分の間合いを作る方法
1-1:相手を押して自分が動く
ルール上相手を押せばカテゴリー2のウォーニングとなりますが、自分が動くための支点を作るために相手を押します。
1-2:蹴りは足の踏み替え
接近戦からの蹴りにおいて足の踏み替えを行うことは、相手の突進をかわす・蹴りの間合いを作る・技の切れと威力を出す等、様々な効果が期待出来ます。
②ゼロの間合いからの中段蹴り
2-1:後ろ足で蹴る
接近した状態から後ろ足で中段を蹴るには、後退する必要があります。しかし実際に後退すると相手に反撃されるリスクがあります。リスク回避する方法として、蹴る方と同じ側の手を前に出して、相手の前進と攻撃を止めながら蹴ります。
2-2:前足で蹴る
前足で直接蹴ると、威力が乏しくポイントに繋がりにくいですが、足を前後にスイッチさせて踏み替え、瞬間的に後ろ足として蹴ります。
ポイントは両足をト・トンと2度踏み替えることです。
③ゼロの間合いからの上段蹴り
3-1:基本的には中段蹴りと同じですが、密着した状態で足を高く上げるため崩されるリスクがあります。
・蹴り足を身体の中心に寄せる
・相手を横に押すと同時に軸足を横に移動させる
・後頭部を蹴る
コツは出来るだけ接近した状態から足を巻き付けるように相手の後頭部を蹴る事です
3-2:後ろ足で蹴る
蹴り足を後ろに引き、次に軸足を後ろ足の位置に引いて蹴ります。この時も、足の踏み替えでト・トンです。上体を倒しながら蹴ることで足がより高く上がり、顔面への攻撃を防ぐ効果もあります。
注意点は、相手に対し上半身を真横に保つことです。
④ゼロの間合いから突きで極める
4-1:押して突く
片手で押して、押した手を使って突きます。後退せず、横に移動しながらです。
ポイントは腰を切らない突き方です。後ろ足のつま先を後ろに向けたまま突けば、上体が横を向いたままなので、速いだけでなく相手に攻撃される心配も少なくなります。
4-2:肘受けで間を作る
前腕の肩から肘までを相手に密着させ、前の足を軸にして後ろ足を外にスライドさせます。
⑤ダッキングされた時
5-1:乗って押す
自分の突きをダッキングで潜られてしまった時、相手の肩の後ろを押して横に移動しスペースを作ります。ポイントは、少々体重を乗せて斜め下に押すことです。
5-2:押して下がる
相手の足が自分の内側に来てしまった場合、前足を払われる恐れがあるので、前足を優先的に逃がす必要があります。ただ前足を引いただけでは、その瞬間に足を掛けられて崩されてしまいますので、足を引く時は手で押すことでより速く相手から離れることが出来ますし、相手の反撃が遅れます。
5-3:押して回る
逆構えで接近した時、相手に外側を取られた場合、より注意が必要です。この場合、相手の肩を押しながら外側へくるりと270°回ります。これで足をかけられる可能性が低くなります。
この頃からルールに変化が生じましたが、密着した瞬間に審判は「分かれて」を発する訳ではありません。
ゼロの間合いを上手く活用して、試合巧者になりたいところですね。