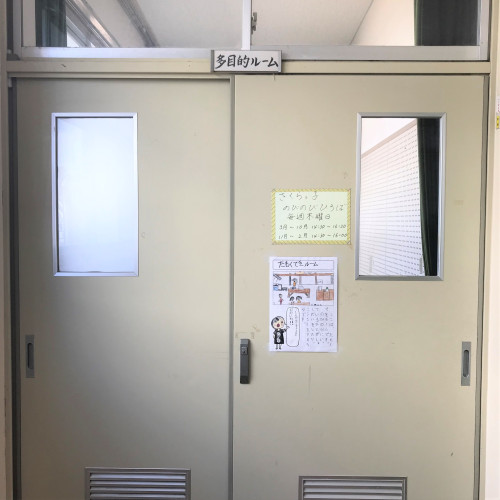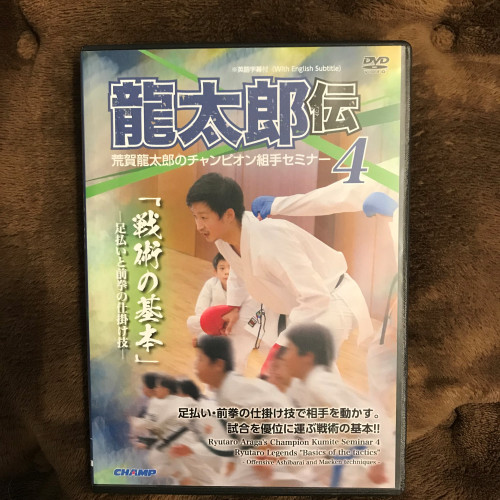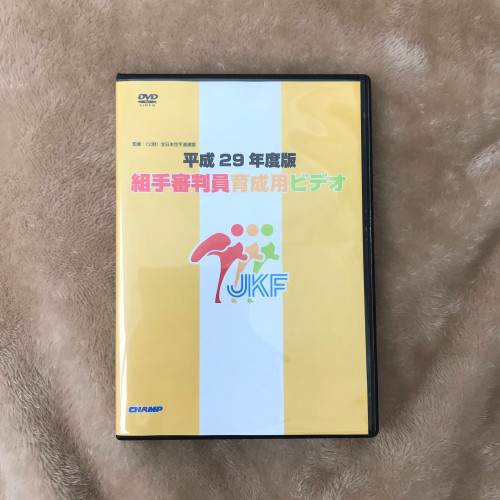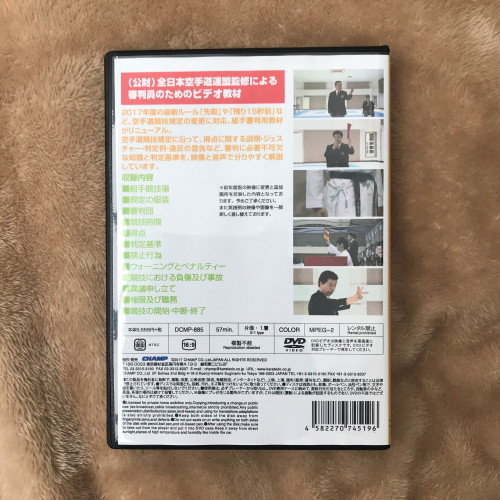ブログ
2023年3月11日 (土)道場稽古45
いつもありがとうございます!
雲ひとつ無い清々しい朝でしたね。
気温もグングン上昇し、ペラペラの組手道着で十分でした。
寒がりの私ですが、ポカポカ陽気の春は花粉に悩まされています。
今年は症状がとても酷く薬が手放せません。
就寝中も鼻が詰まり呼吸困難で目が覚めてしまう程です、、
午前中、修理に出していた原付バイクを受取り
花粉症対策バッチリでいざ道場へ向います!
さて今日から暫くは「多目的ルーム」
エネルギーに満ち溢れる生徒達は、稽古前走り回って遊んでしまいますが、1階は図書室。
稽古以外で騒音を出すと、これから先利用出来なくなると凄くマズいので
【走り回らない】【室内のモノを勝手に触らない】
徹底したいと思います。
股関節・肩甲骨・足首回りのストレッチで稽古前の準備に当てる時間にしたり、早連組と合流するのも有り。
こちらからも生徒には声掛けしていきますので、ご家庭でも同様にお願いいたします。
本日のメニューです
0:早連
1:アジリティトレ
2:筋トレ / 体幹トレ
3:固定式基本
4:形
5:組手
6:居残り稽古
【早連】
正座のおさらいを行ったあと、先週の形稽古で初めて覚えた『四の形』を稽古しました。
中段横受け・突きを4方向に繰り返します。
立ち方は全て『基立ち』
おっと、形に入る前に基立ちの作り方からスタートでした。
1・右膝をつく
2・左足踵を右膝頭に揃える
3・そのまま立つ
4・後ろ足を肩幅に広げる
5・左膝を軽く曲げる
これで、左基立ちの出来上がり!
※右基立ちは単純に足を反対にするだけです
2と4をしっかり身体で覚えるようにしよう。
形は正しい立ち方(長さと幅)が身についていないとダメです。
もうひとつ『前屈立ち』も学びました。
基立ちより、自分の足のサイズ1足分を縦に長く取り、前足の指が隠れる位に膝を曲げます。
何度か基立ちの作り方を練習し、次はいよいよ四の形に移ります!
予め回る方向(左 → 右 → 前 → 後ろ)を説明し形を打ちました。
形を打つ途中、生徒達が次々合流し前や後ろに立ち、合わせてお手本を見せてくれます。
頼もしいですね。自然と私のお手伝いをしてくれます。
立派なお兄ちゃん(お姉ちゃん)です。
ありがとう!
【アジリティトレーニング】
ラダー「シャッフル」で敏捷性を上げていきます。
足の運び方は、
中 → 中 → 外
この順に動かします。
5本程度でしょうか。
正しく動かせる生徒が次に拘るところは、
1・軸を保ち
2・ラダーを踏まず
3・軽やかに
4・素早く
です。
ウォーミングアップには最適ですね。
今日こんなことがありました。
足の運び方がまだよく分からない入会したばかりの女子生徒に、さりげなく教えてくれる1年生の男の子。
早連にも合流し、新入会生の前に立ち形のお手本も見せてくれます。
自然と手を差し伸べる姿を見ていて心も成長しているんだと感じ、私が目指していた町道場のあるべき姿がそこにありました。
この生徒が黒帯になった頃には、下級生達がたくさん集まり慕われる上級生になるんだろうな。
【筋トレ / 体幹】
筋トレは、とうとう大台300回です。
コツは、力を入れる瞬間息を吐くこと。
生徒からのリクエストで体幹はV字プランクから。
良く観察していますと、姿勢がキレイな生徒が先週より増えてることにビックリ!
背筋がピンっと伸びバランスの良いVです。
途中苦しくて足を降ろしそうになっても、自分に負けず耐えています。
努力する姿のなんと美しいことか!
それでこそ我が生徒!
可愛くてたまりません!
他には久々登場のバックプランクとサイドプランク。
最近サイドプランクがイージーになってきた感じ(ええこっちゃ)なので、難易度UP!
5秒かけて片足上げて、5秒かけて足を降ろします。
たったこれだけで、インナーマッスルが更に刺激されます。
目を瞑るだけで更に更に刺激されるよ。
通算82分耐え忍んでいます。
【固定式基本】
先週から意識しだした『キレ』
如何に準備の時間を短くするか。
この一点(これだけじゃないが)に意識を置き、基本稽古です。
形は基本の組合せなので、基本を疎かにすると形は美しいものになりません。
先週に引き続き、美しさに拘った四股立ち突きも60本?だったかな。
少ない回数で、良い基本が出来たのではないでしょうか。
引き手・突き・中段横受け・上段揚げ受け・下段払い受け・四股立ち突きでした。
-奥義は基本にあり-
【形】
形は始まりから終わりまで、全神経を集中させなければいけません。
額から汗が流れても、顔に虫が止まっても余計なことをしてはいけません。
改めてこのことを説明しました。
背筋がピンと張った緊張感ある結び立ちから、姿勢に拘った立礼。
「戦わずして勝つ」の如く、キリっとした表情と発声。
ここも大事にしてほしいところ。
このところ呪文のように唱えています。
一人ひとりの意識が高まるまで形に入らず何度もやり直ししています。
全員の意識が揃ったところで、新入会の生徒を含め四の形!
固定式基本で伝えた準備の時間を短くしキレを意識して形稽古です。
手技のキレに運足のスピードも求めます。
ここ3回前?の平安二段の稽古で取入れている移動足のことね。
次、十二の形に移ったところで新入会組は隣で四の形とグループ分け。
転身のコツをおさらいしながら、一つひとつ丁寧に稽古を重ねます。
技の一致性に加え、今日新たに伝えた『腰の使い方』
この感覚が掴めたら、シャープで極めのある形に変化していきます。
指導形で身体の使い方を身体に染み込ませ、基本形で活かしていきます。
今日の平安二段では基立ちと前屈立ちの使い分け、帯の高さについて説明しています。
緊張感のある形を打てるよう意識高く頑張ろう!
【組手】
先週に続き、拳サポ・シンガード・インステップガード・胴プロテクター・メンホーのフル装備で稽古!
違和感あるでしょうが慣れるしかありません。
大会ではファールカップも着用です。
新入会向けに組手の構え方からおさらい。
組手構えから前・後ろにフットワーク。
注意点を記します。
1・前に進んでも・後ろに下がっても正面に立つ対戦相手から目を離さない
2・前拳・奥拳ともに構えを崩さない
3・膝は軽く曲げたまま
4・カニさんのように寄せ足しない
さぁここからは横の動きに挑戦!
正体揃いのゆり生の中、逆体の私も皆に合わせ頑張って正体となり指導します。
挙動を2つに分け、ゆっくり丁寧に指導したつもりですが如何だったでしょうか。
分かったかな??
フットワークの中で、スッと横の動きが出来るだけで、相手は考える事がひとつ増えます。
組手は相手が嫌がることをやってなんぼです。(反則ちゃうよ)
言い換えれば、自分のペースの掴み合いとも言えます。
同じリズム・同じタイミングで突きを飛ばしても、段々目が慣れてきて相手に攻撃の瞬間を読まれてしまいます。
そんな中、緩急を変えたりフェイントでタイミングをずらしたり、横の動きを混ぜるだけで相手はやりにくくなります。
ワンパターンにならないためにも横の動きは知っておいた方が良いので今日取り入れました。
大会に向け身体に馴染むまで、ゆっくり続けようと思います。
フットワークの次は蹴り!
後ろ足で蹴る、中段回し蹴りです。
ミットめがけて思いっきり蹴るとストレス発散出来ますね!
私も大好きです!
初めて(2回目?)の中段回し蹴りです。
コツを記します。
1・後ろ足で膝蹴り
(蹴りの軌道は正面 最短距離で蹴る)
2・軸足の踵を回しながら後ろ足で蹴る
(踵を回すことで距離が伸びる イコール 突きの間合いの外で蹴れる)
(軸足の膝は曲げたまま)
3・蹴る瞬間 構えた左右の手を入れ替える
(手を前に置くことで突きのカウンターに備える)
4・足の甲(インステップガード)で蹴る
(ミットに小指を当て距離を伸ばす)
蹴りのフォームを学んだあとは、ミットめがけて思いっきり蹴ります!
正面蹴りと同じく、蹴りはスナップを効かせ『ムチ』を飛ばす感覚です。
蹴りは、引き足を取るところまでが『蹴り』です。
蹴った後引き足をとらずに蹴りっぱなしなのは競技ではポイントになりませんので、しっかり意識してね。
「しっかり伸ばして しっかり引く」
注文していた防具を全てお渡ししました。
キズがつくと視認性が悪くなるのでメンホーは下に向けて置かないこと。
それと稽古後、使用した防具を自分で手入れする習慣をつけよう。
これから暑い時期に稽古すると汗でだくだくになります。
一週間カバンの中で放置するとエラいことになるので、ファブリーズで拭き掃除を忘れずにね。
決して親任せにせず自分でやる習慣をつけよう。
【居残り稽古】
今日は形1名・組手3名
5月北区大会で形試合デビューする生徒と平安二段。
・引き手
・前屈立ちの長さ
・下を向かない
まずこの3つを意識して下さい。
4月の審査・5月の大会に向けてもっともっと打ち込もう!
居残りも大歓迎ですし、早く来て形の稽古するのもオッケー!
30分前には居てるよ。
上達に近道なし。稽古した分、上手くなります。
このまま頑張ってほしいです。
他の3名と回さない回し蹴りについて座学です。
何しゃべったでしょうか。
・蹴りのメリット
・蹴りのデメリット
・最短距離で蹴る
・距離を伸ばす方法
だったかな?
保護者の方にも説明しましたが、肩甲骨の使い方ひとつで突きの距離が伸びるように、蹴りも小指の意識ひとつで距離が伸びます。
両手の平を合わせて(親指上向き)手を伸ばし、片手だけ小指を上向きにすると腕が長くなっているはずです。
これは肩甲骨が開いているから。
肩甲骨の使い方ひとつで、距離を稼げます。(腕の付け根は肩甲骨)
この考え方は蹴りにも共通していて、小指で蹴る意識を持つと更に遠い距離から蹴ることが出来ます。
もうひとつ蹴りのフォームについて。
2種類の蹴り方を見せ、区別してもらいました。
要するに、自分の蹴りを素早く相手に到達させるにはどうすれば良いのか?
です。
答えは回り道せず ”最短距離”
直線の軌道で蹴れば回す軌道よりも速く相手に届きます。
モーションは大きいより、小さい方がバレません。
理屈が分かれば、教わったことを意識した上でミット蹴り!
脳みそフル回転!
思考しながら稽古してます!
目をキラキラ輝かせ興味津々で学ぶ生徒と空手が出来て幸せです。
※5月3日開催 神戸市大会の締め切りは来週3月18日(土)まで。
挑戦者求む!!
2023年3月4日 (土)道場稽古44
いつもありがとうございます!
大会に向けて発注していた防具類が大量に到着。
大会から逆算して計画的に試合形式の稽古を組む予定にしています。
今はまだ、基本的な技の習得とフットワーク中心の段階ですが本番に向けてフル装備で稽古しています。
なんかロボットみたいで可愛いですね。
それと今朝、新入会2人の道着も到着です。
まっさらな道着を身に纏い元気よく稽古開始!
0・早連
1・アジリティトレーニング
2・筋トレ / 体幹トレ
3・固定式基本
4・形
5・組手
6・居残り稽古
【早連】
新入会の女の子2名の道着が到着!
道着のたたみ方と帯の締め方を説明しました。
やっぱり自然と笑顔がこぼれますね。
道着に着替えたあとは、道場のルールを説明です。
体育館入口前で検温し、体温を名簿に記入・消毒した後入館してください。
道場の扉を開けたら、一礼して入室します。
続いて指導者の元へ向い、元気よく
「押忍!」と挨拶してください。
途中、トイレで席を外す時も一礼を忘れずに。
(出入りは必ず一礼を心がけてください)
稽古終了後は、指導者の元へ向い
「押忍 ありがとうございました!」
指導者との会話では、理解出来た時の返事は
「はい!」です。
指導を受ける時は、直立不動で先生の目を見てお話を聞くようにしてください。
手遊びや帯を触ったりしていては、お話が右から左に流れていき頭に残らないので、お話を聞く時の態度は特に重要視しています。
その場に座る時は正座。
足を崩しても良いと言われましたら、その場で座礼して足を崩すようにしてください。
(女の子もお父さん座りね)
正座・座礼・立礼・立ち方6種・引き手・突き・中段横受け・上段揚げ受け・下段払いで時間となりました。
もう少し立ち方を学んだ後、形に移行したいと思います。
【アジリティトレーニング】
組手に必要な能力に挙げられる敏捷性と反応力。
プレゴールデンエイジ期にあたるゆり生に取って必要不可欠なメニューです。
敏捷性と反応の稽古を交互で取り入れるつもりでしたが、ぎこちなさが取れてきた生徒が増えてきている事もありラダーを選択。
シャッフル一択でした。
注意するポイントは、
・軸ブレしない
・足の裏と床との接地時間を短く
・つま先立ち
・ラダーを踏まない
【筋トレ / 体幹トレ】
いつもの如く筋トレを各10回ずつ。
290回経過。来週で大台300回ですね。
皆のお手本にしたいくらいの体幹力を見せてくれる生徒がいます。
かなりキツいV字プランクですが、顔を真っ赤にして耐え忍びます。
まさに押忍の精神。自分に負けず厳しく出来る生徒です。
とても軸がキレいな生徒。これだけ軸が整っていると近い将来、形で力を発揮しそうな予感がします。
プランク・V字プランク・サイドプランクを各1分ずつ。
皆も、この生徒に負けずに食らいついて来てほしいですね。
79分経過です。
【固定式基本】
今日はとても実りのある固定式基本だったと思います。
かなりキツい四股立ち突き。60本超えてたと思います。折れそうな気持ちに打ち勝ち歯を食いしばってついて来てくれます。
最後もう一度、四股立ちの作り方・角度や高さを説明し、集中して10本。
しんどい基本稽古の最後の最後に抜群の四股立ちを見せてくれました。
説明したことを記しますので、頭にたたきこんでください。
・膝頭と足首は縦一直線
・つま先の角度は45度
・前傾しない
・お尻を後ろに突き出す(背骨のラインを見せる)
・四股立ちは浅すぎず深すぎず
・足首と鼠径部をロックする(フラフラしない)
・猫背にならず肩甲骨を寄せる
・長さは基立ちから拳3つ分
・膝を外側に張る
これらを意識した四股立ちを全員で最後に10本。
キツい稽古を乗り越えたら、当然上達しますし自分に自信が持てるはず。
毎回これの繰り返しで、ちっちゃい山を乗り越え続けます。
いつの間にか筋力がつきキツい稽古が ”普通” にこなせるようになっている事でしょう。
他には突き・中段横受け・上段揚げ受け・下段払い・基立ち / 正面蹴りでした。
今日基本稽古の中で、初めて説明することがありました。
”キレ”についてです。
キレとは動きだしの速さを指します。
いつもと同じ固定式基本ですが、意識ひとつでキレが生まれます。
新入会の生徒には??だったことと思いますが、2年目を迎える生徒に向けて、形競技に役立つキレについて指導しました。
無意識レベルで稽古出来るようになるまで、生徒の頭の中に刷り込んでいきたいと思います。
【形】
全員で四の形・十二の形で技の極め方を学びます。
いつも同じことをしていますので、順番を覚えた人が次に意識することは技のキレ・極め・スピードです。
今日も何度も言いましたが、意識ひとつで成長速度は異なってきます。
質問にもスラスラ答えられる生徒ばかりです。
大事なポイントは頭に入っているなら、身体で表現出来るように意識して取り組むだけ。
寝てても(目を瞑ってても)基本がスラスラ出来る位にまで四の形・十二の形で身体に叩き込もう。
もう少ししたら質を追求していきますが、今は寝てても打てるくらいになるまで量をこなす時期とも言えます。
私の言葉の意味が頭と身体でスッと理解が出来るまでは"量”も必要だとも言えます。
教わったことを忠実に自宅で復習してくれたら嬉しいです。
指導形(四の形・十二の形)でのポイントを記します。
・移動は全て基立ち
・転身時(方向転換)も全て肩幅に立つ
・運足は半円を描く
ここから2グループに分かれて形稽古。
大会参加組と新入会組。
新入会の生徒と四の形です。
初めての形指導。
今まで他の生徒の見様見真似で稽古させていましたが、短い時間でしたが一緒に頑張りました。
今、早連やってますが、基本技と立ち方を覚えたら”四の形”をガッツリ稽古して全体稽古に備えます。
次は、平安二段組です。
全体でひと挙動ずつ。
立ち方とメリハリ(緩急)を意識しながら。
時間配分がここ最近の課題です。
今、基本を固める時期ですが大会が近づいてくると競技に向けた稽古も必要となります。
ゆりは週に1度しかないのがジレンマ。
どないかして2回したいなぁ。
【組手】
構え方とフットワークからスタート。
刻み突きと中段逆突きを稽古しました。
「構え方」
・相手に対して身体は真横に向ける
・顔だけ正面に向ける
・前拳は肘を軽く曲げて顎の高さ
・奥拳は胸の前
・つま先はㇵの字に開く
・スタンス幅は動きやすい程度に広げる
・両膝は軽く曲げる
・踵を軽く浮かす
「フットワーク」
・上に跳ぶのではなく、浮かした踵を踏み込むように沈む
・前進する際、幅を変えず一定
・両膝の溜めは維持したまま
・動かして良いのは足首だけ
・床に接地する時間を短く
・大きくでは無く、小さく速く動かす
「刻み突き」
・軽く曲げた肘を真っ直ぐ伸ばす
・突く瞬間前足を大きく踏み込む
・突き + 踏み込み + 気合の声 で1セット
・突いた時に姿勢は真横
「中段逆突き」
・真横で構えたまま前足を大きく前に運ぶ
・突く瞬間おへその向きは正面
・突いた時、上半身は真っ直ぐを保つ
・突く瞬間、前拳で引き手を取る
・突いた時、軸足親指の腹で身体を支える
組手基本をおさらいした後、ブザーに合わせて互いに向かい合って刻み突きと中段逆突きです。
途中軽くフットワークを取りながら。
メンホーにも慣れる必要があるので防具一式つけての稽古でした。
【居残り稽古】
今日はミットを持参していましたので、ミットの打ち込みをしようと思ってましたが、
その場で生徒からのリクエストがあり形!
大会に向け平安二段です。
決して強制ではない居残り稽古。
今日は5人も参加者が!
随分浸透してきたようです!
特に覚えていてほしいこと。
第一挙動で素早く猫足立ちになる方法を指導しました。
どうすれば素早く回れるのか、コツを理解出来たでしょうか。
形競技は、始めと終わりのインパクトが特に大事だと言われています。
スピード(キレ)があって、
力強さ(極め)があって、
技の一致性(手技・引き手・軸足の張り)があれば
審判におっ!と思わせることが出来ます。
そんな細かい部分の指導をした後、形競技の所作を稽古しました。
入退場の仕方、礼、発声、目付です。
このブログを書いててひとつ忘れていたことがありました。
「歩き方」です。
立礼に角度があるのと同様に、歩き方にも歩幅や腕を振る角度があります。
次回指導したいと思います。
試合当日、堂々と演武出来るよう経験を積み自信をつけさせたいと思います。
ゆり道場では、空手道に興味をお持ちの方を引き続き募集しています。
習い事として武道を選ばれる理由に「礼儀作法を学ばせたい」が良く挙げられます。
私が開設を志した理由のひとつに、地域社会への貢献がありました。
空手教室を通じて私の元に集まってくれた生徒に、将来社会に出て必要とされる・愛される人材になれるよう想いを込めて人間教育を続けています。
・自ら進んで挨拶が出来る
・靴ならべが出来る
・人前でお手本を披露出来る
・敬語でお話が出来る
・人の手助けが出来る
・落ち着いて人の話が聞ける
・リーダーシップの発揮
普段の稽古の中から、生徒にいろんなこと問いかけることで思考させ行動に移させています。
青少年育成に武道はホントに良いと思います。
ぜひ一度ゆり空手にお越しください。
※来週から南館「多目的ルーム」で稽古します!
(ブログの告知カテゴリーに教室までの道案内があります)
教室のものを勝手に触らない!
階下が図書室なので、稽古以外では騒がない!
この2つを守ってね!
2023年2月25日 (土)道場稽古43
こんにちは!
今年に入り空手道に関心をお持ちの方から、数多くお問合せを頂き大変賑やかに稽古させてもらっています。
開設1年目の2022年は10名。2023年に入り既に2名仲間入りです。
今日も新たに女の子が体験会に参加してくれました!
中には事情により、ご縁を結ぶことが出来なかったこともありましたが、彼女のこれからの空手道人生がより良いものになりますよう心から願っています。
さて体験の女の子とともに、早連スタート!
正座の仕方から座礼・立礼へと移り、拳の握り方・引き手・突き・中段横受け・上段揚げ受け・下段払いです。
ドンドン生徒も合流して、お手本を見せてくれる自慢の生徒たちです。
こんなに素直で可愛い生徒達と空手が出来てホントに幸せです。
今日のメニューはこうでした。
1・サーキットトレーニング
2・筋トレ / 体幹トレ
3・固定式基本
4・形
5・組手
6・居残り稽古(組手)
【サーキットトレーニング】
ラダー・ハードル・マーカーを配置し、軽快に駆け抜けます。
ラダー:シャッフル
ハードル:ラテラル
マーカー:フットワーク
組手はスピード感と反射神経が必要ですので、サーキットは持ってこいです。今日は寒かったし。
次回はアジリティ高めのメニューで反射神経を刺激したいと思います。
スピードトレとアジリティを交互にやっていこうかな。
【筋トレ / 体幹トレ】
2人ペアとなり腹筋・背筋・腕立て伏せ・スクワット正面蹴りを10本。
お腹をカチカチに鍛えて突きをもらっても唸らないようにしておこう。
発見しましたよ。
しっかりと胸を床につけ、誰よりも深く腕立て伏せを頑張る生徒を!
いつの間にか、力がついてきたのでしょう。体幹でもキラリと光るものがあります。
今日はプランク・V字プランク・2ポイントプランクでした。
この生徒の持ち味は、真面目で一切手を抜かないこと。
自らの限界に挑戦してくれます。
”最後の敵はいつも自分自身”
私はこの言葉で自分を奮い立たせています。
ストイックに頑張れる生徒にはシンパシーを感じてしまいます。
筋トレは280回、体幹は76分です。
【固定式基本】
平行立ちのポイントをスラスラ答えてくれるようになってきました。
親指を真っ直ぐに向け肩幅に立ちます。
膝を少し緩め、母指球に体重を乗せます。
・引き手
・突き
・中段横受け
・上段揚げ受け
・下段払い
・四股立ち突き
・正面蹴り(平行立ち)
・正面蹴り(基立ち)
生徒が前に立ち、号令をかけてくれますのでピンポイントで修正を加える事が出来ますね。
正面蹴りのポイントを事前に伝えた上で稽古しますが、膝頭がどうしても天井を向かず上手くいきません。
鼠径部の詰まりを取る動きを挟み、もう一度正面蹴りにトライ!
上手くいきましたね!
本人が違いを感じたことだと思います。
股関節が硬い人(四股立ちで膝が内側に向く)は、今日教えた動作をお風呂上りに取り入れてみてください。
四股立ち突きも頑張ってついてきます。途中から数えましたが50本軽く超えてましたね。
しんどくても腰を落として頑張れる生徒は、伸びしろありです。
自分に負けない強い気持ちを養おう!
【形】
4月の審査・5月の北区大会で打つ四の形・十二の形・平安二段を稽古しました。
30分の形稽古の内15分間、全体で合わせます。
・基立ちと前屈立ちの違い
・常に肩幅
・運足のスピード
・手技 / 引き手 / 軸足の締めを揃える
この後、個別稽古に移ります。
時間の都合で全員回れませんでしたが、指摘されたことを自分で意識し修正出来れば上達していきます。
教わったことを忘れずにしてほしいと思います。
今日の指導の中で特に大事にしてほしいところは
【前屈立ちの時の帯の高さ】
基立ちとの違いを出せるようにね。(長さのこと)
基立ち :浅く(軽く前膝曲げる)
前屈立ち:深く(前足の指が隠れる位膝を曲げる)
【組手】
5月の大会に向け、防具をつけて稽古に臨みます。
試合に近い感覚で稽古することで、違和感を緩和するのが狙い。
また防具の脱着、帯なんかも自分で準備出来るよう心がけよう。
おっと!
ゆりの審査目安に書いてますが、白帯の内に自分で帯を締めれるようになってないとオレンジ帯は受けさせませんよ。
(会員ページに目安を添付していますのでご覧ください)
一列に並んでフットワークとバックステップです。
フットワークのコツは、上に跳び跳ねるのではなく足首だけで前進します。
寄せ足せず同じスタンスで行うことも大事です。
フットワークを終えたら次はブザーに合わせ刻み突き。
今度は、上段突きを2本突くワンツーです。
上段 / 中段のワンツーとは異なり、顎の高さを狙います。
刻み突き(真半身)
上段逆突き(真身)
スタンスは深く潜る中段とは違い、その場で前足を2回タップする感じ。
2本目の突きで極めますので、最後は引き手を大きく取る意識です。
一人ひとりミット打ちして本日の稽古を終えました。
これまでに道場で稽古した技はこんな感じ。
・刻み突き
・中段逆突き
・ワンツー(上段 / 中段)
・上々(上段 / 上段)※今日のね
・フットワーク
・間合い
北区大会に向けこれから2種類の蹴りを稽古します。
蹴りが終われば、防具フル装備で試合形式に移っていきます。
(さっきメンホー届いたよ)
※組手競技に出ない生徒は、形競技に向けて頑張ろう!
【居残り稽古】
予めリクエストがあった組手を頑張りました。
間合いの出入りから、刻み突きに入る練習(先週のおさらい)と中段回し蹴りです。
今日の座学はこちら
・蹴り方のコツ
・蹴りの利点
・蹴りの間合い
ざっと1時間弱だったでしょうか。
居残り稽古終了後、やり切った感溢れる笑顔を見せてくれるのでこちらも癒されてます。
来週も組手やろかな!
※ブログを書いてる途中、体験会に来てくれた方から入会の連絡をいただきました!
心を込めて指導に当たらせていただきます!
荒賀龍太郎のチャンピオン組手セミナー4 龍太郎伝 「戦術の基本」-足払いと前拳の仕掛け技- 1/2
こんにちは!
荒賀竜太郎のチャンピオン組手セミナー 前編です。
01:ウォーミングアップ
02:構えをキープして足を触りあう
03:動きながら突きを受ける
04:足元を意識させる足払い → 刻み突き
05:足払い → 刻み突き → 中段蹴り → +αの連続蹴り
【ウォーミングアップ】
・足バタバタ
・ジャンプ
・バービー
・スイッチ
・ダッシュ
・うつ伏せダッシュ
・仰向けダッシュ
【構えをキープして足を触りあう】
-荒賀先生の構え方-
01・スタンスは肩幅大
02・つま先の向き 後ろ足:横(溜めが作りやすい) / 前足:斜め前
03・踵を浮かす
04・膝を軽く曲げる
05・上体はリラックス
06・前拳は肩の高さ
07・前肘は軽く曲げる
08・懐は深く
09・奥拳は中段を守る
10・真半身
11・軸はやや後ろ
組手構えでお互いに向き合い、相手の足を自分の足で触りあう練習です。
動いてもOKですし、相手の足タッチをかわして足払いしてもOKです。
前足・後ろ足、スイッチを使いながら、なるべく触られないように動ける範囲で足元をしっかり動かす練習を行います。
下がった時、触りに行った時、反対構えになって回っても常に構えはキープです。
足のスタンスは一定です。足が広がると、こかされてしまうので。
まずは、構えを意識しながら自由に足元を動かす練習からスタートです。
足払いは蹴りではなく、相手の膝から下を触りにいきます。
自分が触ったあと、相手に触られないように距離を取る事が大事です。
【動きながら突きを受ける】
ペア練習です。
相手は突きだけ。刻み・逆突き・ワンツーなんでもOK。
自分は相手の突きをしっかり受ける練習です。
受けるとは、バックステップ・パーリング・ダッキングを指します。
ポイント1:
相手の攻撃の外側を取ること。また受けた後は、すぐに回り込み距離を取ります。
ポイント2:
相手の突きに対し、真っ直ぐに下がらない。距離を取るために下がっても良いが、最終的には横に切れるようにする。
ポイント3:
ダッキングでは頭を下げるだけでなく、突いてきた手をしっかりガードしておきます。また相手が蹴ってきても手を上げていればガード出来ます。
高学年ともなれば、上体を柔らかく使い受けています。
後ろに下がる時、横に下がる時も手のガードは下げてはいけません。
残り15秒で焦ってしまうと、足も手も動かなくなってポイントを取られてしまうので、攻撃の練習だけでなくディフェンスの練習も必要です。
受ける(捌く)練習・ダッキングの練習・コートを上手く使う練習をしておけば余裕が生まれます。
「あとしばらく」を想定した練習でした。
【足元を意識させる足払い → 刻み突き】
足払いの目的を説明されています。
1・相手を崩す足払い(ころばす、刈る)
2・相手に足を意識さす足払い(技を上下に散らす)
3・もうひとつ相手の心理としては触られると
①ビビる、居つく
②足を引く、身構える
③体勢が崩れる
④下がる・前に出る等反応する
と何らかの現象が起こります。
ここでは、相手を動かしてコントロールするための技として使う足払いを紹介されています。
メリットとしては、駆け引きの中で足払いを用いると相手の反応を探れたり、相手を動かすことが出来ると説明されています。
逆にデメリットもあります。
相手に触るということは逆に攻撃される距離に近づくということです。
いくら足払いのあとに、技を出したとしても技の数としては「いち・に」です。
足払いの「いち」に、相手に技を合わされたらポイントを取られてしまうことを説明されています。
ふむふむ。
上記をふまえた上で技術論に入ります。
①構えた体勢から、寄せ足しないで触る(これが出来たら良いがなかなか難しい)
②自分の前拳で相手の意識を上に持っていき、寄せ足して足を触る
寄せ足出来る分、②の方が簡単です。
ただし2挙動になるので自分の前拳で、相手の前拳を上から蓋します。(相手はカウンターの刻みを狙ってきます)
前拳で相手の突進をブロック出来るので必須ですね。
注意点は、身体から突っ込まず前拳から入ること。
身体から入ると相手はカウンターで反応しやすいですが、前拳から入ると相手は受けなアカン!かわさなアカン!という感覚が働きます。
ここから実際に技に繋げた入り方です。
前足足払い → 刻み突き
まずフットワークから、足払いをして距離を取り、2度目は足を触らず刻み突きを極める入り方を練習していました。
これは、相手に対し距離を惑わしています。
1度目:足払いされ距離が近い認識を持たす
2度目:足払いが届かず遠いと思わせて、刻み突きでポイントを狙いに行きます
1回目は触る・2回目は触らないことで相手は距離感を間違えやすくなり、ポイントに繋げるという訳です。
足払いは、相手の反応を遅らすことが狙いです。
足払いをする時のポイントは、後ろ足の溜めが大事です。
後ろ足の溜めを使って、跳びこみます。
『足払いの姿勢』
足は触っているが、上体は後ろにあってバランスが取りやすい体勢です。
後傾していると相手からしたら距離が遠く突きにくいが、自分は後ろ足に溜めがあるので前に跳びこみやすい。
『攻撃後』
足払いからの刻み突きの後スイッチしてVの字で残心を取ります。
『応用技』
触らない足払いを撒き餌にし、相手が反応して刻み突きを合わしてきても、距離が遠くもらう心配はありません。
そこを捌いて、突きで返すお手本も見せてくれました。
【足払い → 刻み突き → 中段蹴り → +αの連続蹴り】
相手の足を蹴って突いて切り返したら、中段蹴りを繋げます。
流れるように技が出せるようになれば、もうひとつ刻み突きを追加!
こうしてドンドン技が繋がっていけるように繰り返し練習しています。
ここで大事なのが中段蹴り。
ダッキングされた後、切り返しての近間の中段蹴りや後ろに下がった相手に対しての中段蹴りに有効です。
なぜ大事かと言うと、「先取」ルールが出来たから。
相手に選手を取られると、逆転するには2ポイント上回らなければいけません。(中段蹴りは2ポイント)
強い相手に突き技で2つ取るのはしんどいかも知れませんね。
上段蹴りを狙って上を警戒されるより、しっかり下を狙ってポイントを取れるようにすることが重要と説明されていました。
また中段蹴りは、腹部に相手の手があったとしても、音がすると入ったと思わせることが出来ます。
(背後の副審にはタイミングと音でごまかせる?)
確かに上段蹴りの場合、手でガードしていれば旗は上げにくいですね。
なので攻撃終わり(離れ際)の中段蹴りをとても意識されているようです。
あくまでも、足払いに相手の意識を向けさせ突きで極めます。
それにプラスして蹴りで終われるようにします。
注意することは距離。
足で触って突きで跳びこみますが、その後相手との距離によって蹴り方を変えなければいけません。
詰まっているなら相手を押して空間を確保します。
それでも近い場合腰を残して蹴ります。(遠間の蹴りかたでは、抜けてしまうし潰れてしまいます)
距離を見て判断することもポイントです。
平成29年度版 組手審判員育成用ビデオ
こんにちは!
組手審判資格取得に向け、購入したDVDです。
少しばかり古いですが、この平成29年度版がDVDとしては最新です。
悲しいかな、しょっちゅうルールがマイナーチェンジしますので5年も経つと、ところどころ今と異なっています。
このDVDの優れているところは、ルールブックを読んでいても分かりにくい試合中のシュチエーションを、試合形式の動画で再現し答え合わせしてくれます。
やはり文字より動画の方が、頭の中に入ってきやすいです。
ルールブックやDVDで頭に叩き込み、マイナーチェンジした情報をJKFに自分で取りにいかないといけません。
常にアンテナを張り巡らせていないと、変わったことすら気づかない事にも繋がりかねます。
2022年9月の審判講習会で学んだ新ルールから、つい先日開催された栃木国体から、またルールが変わったと聞きます、、
更には、2023年1月にWKF主導で大きくルール変更があると情報が入りました。となれば来年春にはJKFでも改定があることでしょう。
新ルールに対応した練習をしないと組手競技では命取りですね。
※ おっと!年末の全日本からルール変更のようですね、、