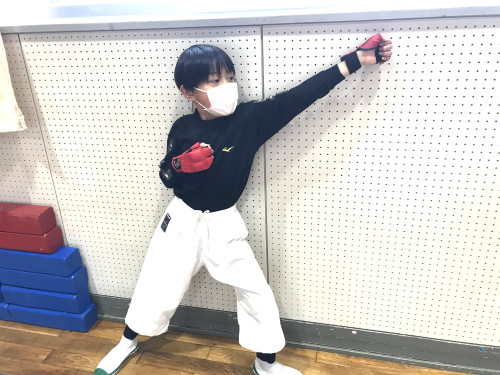ブログ
2024年2月10日 (土)道場稽古88
こんにちは!
今日は1部も2部もガッツリ形稽古でした。
2部では伝えたいことを全部伝えた。
ひとつの形で90分コースでした。
-バンビクラス-
0・早練
1・ウォーミングアップ
2・ラダー
3・体幹
4・形
-モンキークラス-
5・体幹
6・固定式基本
7・形
バンビクラス
【早練】
いつもの2人。
先日の夜練に、一足早く平安五段に進んだH君。
しっかり自主練積んで来ていました。
幼児のMちゃんは全くの初めてでしたが、これがまたビックリ!
ひと挙動ずつ覚え繋げていく進め方が功を奏したのか、一発で追いつきました。
前半パートの右追い突き(気合い)まででしたが、覚えてしまいました。
【ウォーミングアップ】
ブザーに合わせダッシュ!
ブザーが鳴ったら、素早く切り返してまたダッシュ!
ダラダラしたり、ドタドタした走り方ではダメ。
機敏に向きや体勢を立て直し瞬発力を上げることが目的です。
「ブレーキかけて踏ん張って」
散々、繰り返してる体幹を活かす時ね。
前足でしっかり壁を使って、軸がふらつかないようにします。
遊びのようなメニューですが遊びじゃない。
身体をコントロール出来るようになってれば、これから先組手の攻防で多いに役に立つよ。
ストップ & ゴー である。
カエル飛びの連続ジャンプなんかもやったかな。
あと手足でグーパー。
難易度上げて途中で、手はグー・足はパーにしてみたり。
脳みそフル回転!
【ラダートレーニング】
タニラダーが滑らないよう養生テープで固定しました。
短い距離をフルスピードです。
足の回転力を上げるのが目的ね。
足運びを覚えた生徒はスピードを加速させよう。
クイックランとラテラルでした。
【体幹トレーニング】
プランク・サイドプランク・V字プランクで78分経過しました。
動かない体幹トレから、来週あたり動きを加えた中でビタっと止まる体幹に進みたいと思います。
軸とバランス力が必要になります。
【形】
迷ったが固定式基本を割き、残りの30分形に費やしました。
お休み続出で全員揃いませんでしたが、6人で四の形でした。
良い集中力をみせてくれたこともあり、順番を覚えるまでになりました。
今日の注意点を記しておきますので、忘れないでね。
1・第1挙動、右足を一足分前に出して回る(肩幅に立つよ)
2・基立ちは前膝を軽く曲げる
3・突き手(受け手)だけで技は極まらないので、引き手を強く取る
(つづく)
モンキークラス
【体幹トレーニング】
何ということでしょう、、
重たい荷物を引きづって体幹ディスクを持って来ていたのに使っていませんでした。
プランク・サイドプランク・V字プランクで208分経過です。
【固定式基本】
ここ最近から取り入れている腰のキレを増す稽古に、突きを加えました。
平行立ちから左前屈立ちとなり左中段突きを加えます。
突き手をそのままに平行立ちに戻り、今度は右前屈立ち追い突きの要領です。
同じパターンで逆突きも行いました。
立ち方が変わる瞬間に腰の切り替えしと突きのタイミングを合わせる稽古です。
単純な稽古ですが、腰を如何に速く且つ小さくキレるかがポイント。
稽古の質が上がってきました。
目的を見失わないようにね。
しっかり聞いてないとただの突きの練習になっちゃうよ。
この後、突きを出さず立ち方の変化に合わせ、腰のキレを加える稽古なんかも。
平行立ちから前屈立ちを取り、
前屈立ちから猫足立ちに戻す稽古です。
この稽古を自宅で行いますが、右前屈立ちを取る前に、予め右手を差し出しています。
なぜでしょう。
なぜだか上手く説明出来ませんでしたが、今日この指導をしてる時答えを導きだしました。
腰のキレを増す稽古ですので、動かして良い部位は腰だけ。
腰に加え上半身(特に肩)まで動いてはいけません。
腰だけがキレていると、前に差し出した腕は真っ直ぐを保ったまま。
その確認を込めてのことでした。
「一瞬開いて、立ち方とともに締める」
ひたすら重心を落とした深い前屈立ちを繰り返していますので、腰のキレを上げるとともに下半身強化メニューに繋がっています。
2024年の大会スケジュールも本日発表しました。
春の大会に向け、腰のキレと下半身の安定感を強化しよう!
【形】
残りの90分ひたすら平安二段でした。
私のベストと思う平安二段をひと挙動ずつ、しかも一人ずつチェックしながら何度も何度も繰り返す手法を取りました。
1本の形を打つのに費やした時間は60分。
いつも全力で指導していますが、今日は本気の中の本気。
燃え尽きるくらい本気で指導した。
・腰のキレ
・運足のスピード
・軸の乗せ換え
・技の入り方
・逆腰
・瞬間脱力
・水平移動
・転身の入り方
・背筋の緊張感
・美しい姿勢
次、同じだけのエネルギーを割くことが出来るか約束出来ないくらい全力で指導しました。
なので今日の内容はホントに忘れないでほしい。
さてここからは、自主練の時間。
学んだことをひとつずつ確認する作業を繰り返し、最後は通し稽古。
その間、一人ずつグルグル回りながら個別指導でした。
いつも同じこと言ってますが、一回いっかいの稽古、一つひとつの技を大切に空手道と向き合ってほしいと思います。
集中して稽古に励めば上達しますんで。
人によって得手不得手ありますが、一生懸命に聞いてその通り身体を動かせば、形は変わってきます。
指摘される癖は自分で直す努力も怠らずにね。
来週、平安五段もやります。
これは大会シーズンに向けてのこと。
今日分かってもらえたと思いますが、密度の高い稽古を求めると90分かかります。
組手がご無沙汰になりますが、ちょい我慢してね。
2024年2月3日 (土)道場稽古87
こんにちは!
先週の疲れが出たのかな。
体調崩しました。
-バンビクラス-
0・早練
1・ラダー
2・体幹
3・固定式基本
4・形
-モンキークラス-
5・ラダー
6・体幹
7・固定式基本
8・形
9・組手
バンビクラス
【早練】
リクエストがあり平安二段を。
3人で始まり最終的には6人合流した本日の早練。
ひと挙動ずつ立ち方と引き手の強さを意識して形を打ちました。
転身時の角度と四股立ち移動に難がありましたが、ピリッとしてきた印象です。
【ラダートレーニング】
昨年夏に3つ購入した10mラダー。
幼児には距離が長すぎると、体力が持たずスピード強化には不向きかと感じました。
今日は4マスラダー投入です。
このタニラダー紐じゃないので体育館向きじゃないかな。
ラダーを踏んでしまうとすぐ乱れるし滑ってしまいます。
シューズ履いて外でやるのに向いてるかな。
短い距離をフルスピードで、
クイックラン
グーパー
ラテラル
ラテラル2イン2アウト
【体幹トレーニング】
V字プランク・サイドプランク・プランクで75分経過です。
しんどいV字プランクですが、先週よりも粘りを見せてくれました。
悶絶しながらも足を床につけず頑張ってます。
「自分に負けない」
声掛けひとつで、もうひと頑張りしてくれます。
諦めないようケツ叩いてます。
【固定式基本】
しょっぱなから四股立ち突き!
10まで数えてもう終わりかな?
と思わせといてまた1から。
40本くらい突いたかな。
しんどい時こそ大きな声で気合出すと何とか持ちこたえられます。
こっちが嬉しくなるくらいのホントにデカい声出ます。
ここからはいつもの突き・受け3種でした。
正面蹴りもいつものメニューですがサッカーボールを蹴るような癖が抜けきらず、膝の抱え込みの指導にひと工夫加えました。
胸の高さに手のひらを固定させ、膝頭を垂直にぶつけてみることに。
これが予想を上回る効果が。
どうやら伝わったようです。
蹴りの前にストレッチで股関節のつまりを取ると、もっと良い蹴りが出せそうです。
【形】
今日のバンビ空手。終始緊張感を保ちながら稽古出来ました。
形に入る時の表情も凛とした佇まいです。
背筋のラインや、指の先までピンと伸ばし、形のコールはお腹に力を込めて発声です。
当然立礼の角度にも拘りを持ちながら。
前後にお手本のお兄ちゃんお姉ちゃんに立ってもらいながら、全力で四の形を5本打ちました。
1本目より2本目。
2本目よりも3本目とより緊張感のある立派な形でした。
張り詰めた空気感の中、良い稽古が出来たと思います。
(つづく)
モンキークラス
【ラダートレーニング】
今週も思いおもいにラダーを駆け抜けます。
メニューにひとつアウトターンを加えました。
前足動かせばインターン、後ろ足ならアウトターンね。
「軽やかに」が基本ですが、ひとつ注文を。
シャッフルで外に開くとき、重心が振られていてはバランスを崩しますので組手競技で不利に働きます。
外側にしっかり「壁」を作る意識でシャッフルしました。
ここでも散々取り入れている体幹力が試されます。
意識をどこに置くかで効果も違ってくるんじゃないかと思います。
【体幹トレーニング】
バックフルアップ・V字プランク・プランクで205分経過しました。
プランクは床と平行に姿勢を保ち猫背改善を意識して。
姿勢が悪いと美しい形は打てないよ。
【固定式基本】
今日は下半身トレを行わず、腰のキレを磨く時間に充てました。
前屈立ちを極める時の腰のキレから猫足立ちに戻す時のキレです。
上半身・下半身を固定して腰のみを切る練習を引き続き行っています。
骨盤操作を具体的に理解してもらうために、お尻歩きを行いました。
踵を床に着けずお尻だけで前進と後退を繰り返し、動かし方を身体に摺り込みます。
その後、また前述の立ち方を極める練習に戻り、感覚を養いました。
ひたすら腰のキレ磨きに時間を割きつつ、従来の基本もしっかりと。
両拳を正中線且つ鳩尾の高さに揃え突きのコースを身につける練習と、この日は中段横受けの深堀りを。
初級に教える中段横受けとは少し異なります。
「ゆっくり基本」で動作を一人ずつチェックしながら、最後は全力スピードでした。
【形】
30分形の時間でした。
平安二段と平安五段です。
挙動ごとの注意点を説明しながらブザーに合わせました。
今はこのやり方がベストかと思います。
コツを意識した上で「通し稽古」しないと悪い癖がより悪くなってしまうと考えています。
形にキレが必要なことは基本稽古で学んでいますので、運足のスピードや軸の移し替え、技に入る準備時間を短くすること等、形稽古の際中に意識付けしないといけません。
転身しながら下段払いに入る方法や、猫足立ちのタイミングに合わせて力強く横受けに入るコツを繰り返し稽古しました。
今年に入り、生徒の集中力が高まっています。
良い緊張感の中、稽古出来ています。
【組手】
この日のメニューは、
組手基本・間合い・刻み突きの3つを60分かけて練習しました。
試合では60秒休むことなく動きっぱなし。
基本が身についてないと、腰が浮いたり構えが下がったり。
疲れた時でも構えが崩れないよう、時間をかけて組手基本しています。
正しく構え、突いた後は正しい位置に戻るだけ。
膝の溜めを作って、軽く曲げた肘を伸ばして突いて、またそこに戻すだけ。
寝てても出来るくらいに身体に染み込ませないと春の大会間に合わないよ。
構えが下がってたら反応遅れるし、膝が伸び上がってたら組手に必要な爆発力が不足します。
絶対に雑になってはダメ。
突き3種類、突き蹴りのコンビネーションで20分かけたかな。
次に刻み突きのフォームについて改めて説明しました。
真半身と真身の突き方について、どこがどう違うか説明しました。
シンプルに構えた位置から肘を飛ばすだけ。
後方の副審にも長い突きを見せなければ旗は上げてもらえない。
エビのように真身で背中を丸めて突く癖を自分で意識して直せるようになると、ひと皮剥けるんじゃないかな。
後、突いた腕は肘を引く感覚ね。
下に降ろすと軌道が悪く旗が上がりにくい。
一本いっぽん丁寧に基本練習を行い修正してほしいと思います。
ペア練では、前後のフットワークの中から前に跳びこむタイミングと距離を測る練習でした。
組手する距離については、散々説明しています。
間合いの出入りを繰り返し行い、刻み突きを5㎝手前にコントロールする練習です。
どの距離で組手すれば良いのか。
自分の身長や脚力を知ることが何より重要です。
失点するリスクを軽減しようとすれば、遠い距離から飛び込めれば良いですが、脚力が無いと届きません(ポイントにならない)
前後に駆け引きする中でいろいろ距離を調整出来ればGoodです。
そろそろ、そのあたりの空手脳が必要になってくるかな。
考えながら動きを試せる人は、成長速度は絶対に早いでしょうね。
道場に天才はいてませんので、練習の意図を理解しあれこれ自分で試行錯誤出来る人になってほしいです。
そんな声掛けしていかなあきませんね。
点と点を線に結びつけられる人は、どんな練習でも手を抜かなくなるはずだ。
2024年1月27日 (土)道場稽古86
こんにちは!
今日は体調不良続出で少し寂しい人数でした。
なんか今日は裸足で稽古する生徒が多かったような気がします。
-バンビクラス-
00・早練
01・ウォーミングアップ
02・ラダー
03・アジリティ
04・体幹
05・固定式基本
-モンキークラス-
06・ラダー
07・体幹
08・固定式基本
09・移動式基本
10・形
バンビクラス
【早練】
このクラスでは、空手道の基礎を学ぶとともに「動ける身体作り」も行います。
スピード・体幹力・反射神経等いろいろな要素があります。
急な方向転換しても身体に壁を作り軸で止まれないといけません。
頭の中でどう動くか指令を出し素早く身体が反応出来れば、どんどん動ける身体になっていきます。
イメージ通り動けるようになろう。
動ける身体作りが直近の目標ね。
1・聞く力
2・考える力
3・運動神経
この3つ、見込みが無いと上のクラスに上がってもついていけません。
(幼児は楽しく稽古出来れば十分だよ)
大縄跳びでした。
中に入るタイミング
ジャンプするタイミング
外に飛び出すタイミング
上手に出来る人がどんなタイミングで飛んでるかよく見てみよう。
考える力ね。
楽しく遊びながら、考える練習もね。
【ウォーミングアップ】
足上げ・ダッシュ・サイドステップ・バックステップ・ジャンプ・抱え込みジャンプ・カエル飛びジャンプでした。
組手が活きてくるようジャンプ系を取り入れています。
反応速度や一歩目のスタートが速くなるよう、うつ伏せ・仰向けダッシュを取り入れました。
これが速い子は組手に活きてきます。
ブザーに素早く反応出来るようにね。
みんな意識は高かったかな。
隣の子よりも速く!
【ラダートレーニング】
・クイックラン
・グーパー
・クロスカントリー
初めてのクロスカントリー。
(横向きで足を入れ替えるやつね)
説明してる時に『よく聞く』ように。
よく聞いて脳みそフル回転ね。
【アジリティ】
4色コーンを使って十字ランダムでした。
これかなり久しぶりだったと思う。
反応スピードを鍛えてます。
中腰でサイドランが出来たらもっとスピードが上がるが、それはまだ早かった。
ゲームは単純で指定された色をタッチするだけ。
中腰で体軸使ってブレーキをかけれると、反応力とスピード力が上がります。
モンキークラスの3年生にもやってもらいましたが、さすがでした!
良いお手本だったです。
動きに慣れてきたところで、脳トレを挟みます。
今度は、指定された色の反対色をタッチ!
赤なら青、緑なら黄といった具合です。
反応力にプラスして判断力も磨きました。
咄嗟の判断は、コートの中を目まぐるしく動き、どんな体勢からでも攻撃や防御をするといった状況に役立ちます。
これも頭の回転と身体を同時に操る、コーディネーショントレーニングのひとつです。
それにしても、幼児のMちゃん良い反応してましたね。
反対色も間違えることなく、瞬時に判断出来ていた。
脳トレとコーディネーショントレーニングの量を増やし、もっと動ける身体にしていきたいと思います。
凄く成長してる!
【体幹トレーニング】
72分経過。
V字プランク・サイドプランク・プランクでした。
毎回、生徒が選ぶ体幹メニューですが、一番キツいV字プランクが毎週出てきます。
ストイックで良いですね。
頑張りは全部自分の身体に返ってきます。
体幹頑張れば、微動だにしない立派な軸が出来ますし、
人の倍基本を頑張れば、美しい姿勢となって力がつきます。
毎日少しだけでも良いので、何か継続してみよう。
何でも構いません。
「休まない」・「コツコツ継続できる」
これが出来る人は、自分の肉体や繰り出す技に変化が出てきますので、観てたら直ぐに分かります。
正しい努力で自分に自信をつけよう。
出来ないことを出来ないままにしない。
体幹トレの継続なんかすごく良いと思います。
家でテレビでも観ながらV字プランク、漫画でも読みながらサイドプランクなんか良いんちゃいますか。
【固定式基本】
動ける身体作りに40分近くかけ残り20分は空手の基本!
いつもと違う突きの練習をひとつ取り入れました。
引き手を取らない突きの練習です。
目的は正しい突きのコースを身体に落とし込むためです。
生徒全員に今年の目標を書いてきてもらった中に、
大会に出場出来るくらいになりたいと願う生徒がいました。
それならば、もっと分かりやすく基本を指導しないといけないと感じた私は、いつもと違う突き方でアプローチしました。
正中線且つ鳩尾の高さに拳を置き、次の突きの目安にします。
突いた瞬間、両拳が揃っていればオッケー。
初めての試みでしたが理解出来たかな。
これも聞く力・考える力を発揮してもらわないといけません。
突きの位置を学んだあとは、いつもの通り引き手を使った突きの練習に移りました。
他にも四股立ち突き・中段横受け・上段揚げ受け・下段払い・左右正面蹴りで本日の稽古を終えました。
もっと幼児が理解し易い言葉を探したり、身振り手振りを加えて伝わるよう私も更なる勉強が必要です。
私も頑張ります。
(つづく)
モンキークラス
【ラダートレーニング】
ラン系、ツイスト系、ジャンプ系と、各自思いおもいにラダーで身体を温めました。
正確性とスピードを意識しないといけません。
シャッフルでは左右の切り替えしで敏捷性を高めながらも身体を外側で支え、軸をブラさずコントロールしないといけません。
ここでも軸が出てきますね。
スピードに乗って自分の身体をコントロール出来るようになろう。
短い時間で切り上げました。
【体幹トレーニング】
V字プランク・2ポイントプランク・プランクで202分経過。
とうとう大台に乗りました。
ジッと身体を支える体幹トレから、軸をブラさず動きを加えた体幹トレまでこなしています。
2ポイントプランクでは、伸ばした手足をおへその下でタッチする動きを織り交ぜ、難易度を高めました。
【固定式基本】
始めに腰の使い方を指導しました。
でんでん太鼓の要領で腰だけを動かす練習に時間をかけました。
両手を身体の前で握りツイスト。
次のステップは腰を左右に大きく動かし、ピタっと動きを止めたら横払いを極めます。
手技は、下半身から極めます。
足 → 腰 → 手
下から上の順に力が伝わるイメージです。
腰が極まったあと、少し遅れて腕がしなるような動作です。
段々腰の動きを小さくしていきたいところですが、そう簡単ではありません。
(行き)平行立ち → 右前屈立ち
(帰り)右前屈立ち → 右猫足立ち
往復で2回腰を切る練習を行いました。
形競技では、学年が上がるとキレが無いと勝つことが難しくなってきます。
コンパクトに素早く腰だけを切れないとダメです。
頭のてっぺんから串刺しになった状態で腰のみを動かせないといけません。
この練習だけで30分かけたかな。
(行き)平行立ち → 四股立ち
(帰り)四股立ち → 右猫足立ち
これもやったか。
骨盤を動かす良い練習がありますので、次週続きをやる前に骨盤運動取り入れます。
骨盤を自在に操れないと前進・後退出来ない運動です。
24日の夜練では極めを上げるミットトレーニングに入り、今日キレを磨くメニューを取り入れました。
形には、キレ・極め・スピードが必要ですが、この後の移動基本でスピードを上げる方法を指導しました。
本日の下半身強化は、屈伸突きでした。
後屈立ちに近い状態から、前屈立ちで逆突きします。
沈む時も軸が串刺しのイメージを持とう。
左右合わせて40本近く突いたでしょうか。
やはり基本が大事です。
【移動式基本】
正しい立ち方を身につけるには、移動基本がベスト。
基立ち・猫足立ち・四股立ちでした。
途中片膝をつき、正しい長さが取れているか確認を挟みます。
今日取り入れた腰のキレの使いどころでもありましたが、どうだったかな。
下半身と手技を連動させられるように。
平安二段の見せ所のひとつ、四股立ち。
やってはいけない動き方と、逆にこれから意識してほしい動き方について説明しました。
どうすれば前進するスピードが上がるのか、指導しています。
これは、これから先学ぶ糸東流第一指定形のセイエンチンで多いに役立ちます。
セイエンチンでは四股立ちで前進・後退する挙動が計4か所出てきます。
全体的にゆったりとした重厚感溢れる形ですので、この四股立ち移動でスピードの違いを表現出来ないといけません。
最初から最後まで単調なリズムですと、観てる方も退屈する極めて難しい形とも言えます。
近い将来のこともありますので、今日の移動基本を忘れないようにしてね。
応用が利きますので。
【形】
何分やったかな?50分程度形だったような。
ほぼフリーの時間を取りました。
誰一人おしゃべりすることなく、集中出来ていた。
大半の時間を最近2部に上がってきたSちゃんに平安五段をミッチリと。
初めての技や立ち方がありますので、まずは名前と順番を覚えていこう。
順番さえ覚えれば、全員で形を合わせられます。
家で練習しなかったら、また最初からやり直し。
そうならないように、自主練やってくるようにね。
20分かけて他の生徒一人ひとりまわり、アドバイスしています。
全体に言えるアドバイスをひとつだけ。
肩甲骨を意識して形を打ってみよう。
受け技では寄せて、肩甲骨から突くと大きな技が表現出来るよ。
意識一つで形の見栄えが変わります。
小学校入学前に出会った生徒たちが、この春3年生です。
真剣なまなざしで稽古している姿を観ていると成長したなと感じる。
自分の開いた教室で一生懸命、空手道に向き合う姿を見ているとやりがいを感じます。
ありがとう。
2024年1月20日 (土)道場稽古85
こんにちは!
ずっとリクエスト受けていた大繩を久しぶりに投入!
稽古前にアップがてらバンビたちと跳ぶことに。
これまでジャンプのタイミングがつかめずにいましたが、どういうことでしょうか幼児のMちゃんと1年生組が跳べるようになっていました!
確か初登場したのは半年ほど前だったかと。
体育の授業や道場稽古、普段の遊びの中でいつの間にか運動神経が上がっていたんでしょうね。
後半、幼児組がたくさんやってきたので「へび」したりでした。
また本日、お足元が悪いなか体験生2名お越しいただきました。
流れに乗って体験生もスッと縄跳びに入ってきてくれ皆と一緒に遊ぶことに。
同年齢、習い始めたばかりの生徒で構成されるバンビクラス。
このクラスでは空手道の基本を反復練習するとともに、思いっきり身体を動かす全身運動や礼儀作法を学びます。
楽しみながら行えるプレゴールデンエイジ期向けの練習をたくさん取り入れています。
空手教室ですが60分のうち1/3は運動神経向上のメニューです。
体幹や反射神経・運動神経はあらゆるスポーツに共通する土台となる部分ですので、コーディネーショントレーニングによって脳神経をどんどん刺激していきます。
一見、体操教室に思われるかと思いますが「今」やっておくべき運動です。
-バンビクラス-
00・早練
01・ウォーミングアップ
02・体幹トレーニング
03・固定式基本
04・ラダー
05・組手
-モンキークラス-
06・ラダー
07・体幹トレ
08・固定式基本
09・形
10・組手
バンビクラス
【早練】
今週の早練は大繩でした。
何回回したのでしょうか。
帰ったら肩がパンパンです、、
飛べなかった生徒が飛べたり、中に入るタイミングが掴めなかったのに入れるようになってた。
成長を感じた瞬間です。
いろんな生徒の成長してる姿を見ていると、教室開いて良かったと思える瞬間です。
思いっ切り飛んで跳ねてジャンプして潜って、大笑いしながら遊びの中で運動神経上げてます。
【ウォーミングアップ】
寒いので、道場をグルグルとジョグ・ダッシュ・サイドステップ・バックラン。
今度は横一列に並んで、ジャンプ・カエル飛びジャンプで腸腰筋を刺激します。
このジャンプ、組手する時に必要なスキルです。
突く瞬間、遠くに踏み込みます。
ブザーに合わせて仰向けダッシュ・うつ伏せダッシュなんかも。
これは反応速度を高めています。
音に反応して瞬時に身体を動かします。
子供たちは競い合うのが大好き。
隣の友達より速く!
でも、走るのが速くじゃないよ。音に反応して起き上がる動作を速くね!
【体幹トレーニング】
自重でV字プランク・サイドプランク・プランクで69分経過。
体験生めちゃくちゃ可愛いじゃないですか!
【固定式基本】
正座の仕方から説明しました。
順番は「左座右起」
左足から順に座り、右足から立ち上がります。
途中「跪座」の姿勢を取ります。
これは相手に襲われた場合、素早く立ち上がるために行います。
手をついて座礼する際も左手から。
座礼時の目付は、伸ばした指先の頂点に向けます。
目付を前方にやる理由ですが、相手の気配を察知するためにそう指導しています。
次に立礼。
ピンと伸ばした指先を体側につけ背筋を伸ばします。
立礼の角度は太ももの裏側がピリッとしびれる程度で止め、目付は真下を向けず斜め前です。
これも目付が前方にあれば敵の気配を感じ取れるから。
座礼・立礼のあとは、拳の握り方。
幼児の多い道場ですので、超簡単に3挙動に分けてシンプルに指導しています。
1・4本の指の第一関節を曲げる(爪が見えてる)
2・4本の指を第二関節まで曲げる(爪が隠れてる)
3・親指で人差し指と中指を締める(これ大事)
Aちゃんに前に立ってもらいお手本を披露してもらいました。
引き手・突き・中段横受け・左右正面蹴りでした。
このクラスはとにかく元気!
気合いの声がデカい!
空手教室らしくてこの雰囲気大好きです。
何でもそうですが、気合入っていて損することはありません。
部活でも社会に出ても、気合入ってる子は先輩に可愛がってもらえます。
空手が上手いも下手も関係ありませんので、ずっと継続してほしいと思います。
【ラダートレーニング】
後ろに置いていたラダーをずっと気にしていたMちゃん。
2部で使う予定でしたが、バンビでもすることに。
・クイックラン
・グーパー
・ケンケン
・スラローム
・ラテラル
速く走るコツは、「爪先立ち」と「床への接地時間を短く」です。
【組手】
短い時間でしたが、組手構えとなり刻み突きとワンツーを出したところでタイムアップ。
ホントに短い時間ですが、これで3週続けて組手の稽古をしています。
真っ直ぐ突きを出せるようになったら、実際にミットを突いていきたいと思います。
(つづく)
モンキークラス
【ラダートレーニング】
身体も冷えてることでしょうしラダーからスタートです。
・クイックラン
・グーパー
・シャッフル
・2イン2アウト
・ラテラル2イン2アウト
なんかをそれぞれ2本ずつ。
2本目は後ろ向きでした。
神経系トレのおかげで組手の反応上がってきてると思います。
【体幹トレーニング】
V字プランク・バックフルアップ・プランクで199分経過。
来週大台に乗りますね!
「塵も積もれば」ですね。
フラフラする子も少なくなっていて、確実に力がついていると言えます。
整った軸、ピタっと止まれる極めの強さを形に活かしていきます。
1・体幹トレで土台作りしながら
2・移動基本で軸の乗せ換えや軸移動・極めの感覚を身体に落とし込み
3・形稽古の中で細かいテクニックや緩急等の色付けを行います
全ての稽古は形の表現力UPに繋がっていきますので、形を忘れたり基本が間違っていたりすると3番に到達しません。
【固定式基本】
年が明けて以降、良い緊張感の中で基本が出来ています。
入門当初はまだまだ幼かった生徒たちですが、凛々しい顔つきで稽古に臨んでくれています。
他所の道場からしたら当たり前かも知れませんが、ふざけたりおしゃべりに夢中になったりが無くなってきた。
この日も短時間集中型で基本を頑張りました。
ここ最近、基本の難易度を上げています。
突いたその手で受け3種です。
右中段突き → 右中段横受け → 右上段揚げ受け → 右下段払い
これを細かいテクニックを駆使しながら極めていきます。
中段横受けでは、前回指導した技にプラスひとつ加えました。
ここでのテクニックは、基本中の基本から逸脱しています。
形競技におけるキレの出し方です。
ホントに正しい受け方かといえばそうじゃありません。
基本と形競技とは似て異なるものかも知れません。
上手く使えるとキレが格段に上がります。
前屈立ちとなり斜角突きです。
これは下半身強化でもあります。
しんどいところで、どれだけ自分に厳しく出来るかが問われています。
四股立ち突きも然り。
まだまだ汗が噴き出すくらい追い込んでいませんが、もっと下半身が強くなってきたら強度を上げていきたいと思います。
「自分に負けない」
最後の敵はいつも自分自身です。
【形】
なんとここまで予定通り時間が進んでいます。
30分形の時間を取り組手を60分かけるつもりでした。
平安初段から順に基本形を全員で打ちました。
本気で力を込めて打つ生徒、
順番をなぞるだけの生徒、
順番を思い出しながら打つ生徒、
まだまだ基本が身についていない生徒
バラバラでしたが、今日のような一発勝負の稽古でも普段通り打てるようにしておいてほしいところ。
基本形に共通する挙動をひとつだけ集中して強化しました。
形競技では、最初と最後のインパクトはとても印象に残ります。
ここで違いを見せれるようにするための練習でした。
求められるのは、
・軸が乗った美しい姿勢
・方向転換するスピード
・タイミング
どうすれば良いのか答えを伝えたうえで何度も稽古しました。
答えを聞いたうえで忠実にトライする生徒と、意識していない生徒に分かれてしまいますが、ここから先は自分次第です。
全体稽古の中で平等に指導していますので、聞き漏らさず習ったことは実践してみてください。
部分稽古はそのための時間です。
なにも考えずに出来る人は「天才」です。
そうじゃないんなら、しっかり説明を聞けるようになろう。
聞いたことを頭の中で整理してから実践ね!
これが普段から身についているか否かで、成長速度は大きく異なります。
何も考えない人・右から左に抜けていく人は要注意です。
【組手】
組手基本・2人組・3人組が今日の予定でした。
丁度1時間ありましたので、最後まで行けるかと思っていましたが組手基本と2人組まででした。
組手基本は、先日の夜練と同じメニューでした。
正しく構えて正しく突く(蹴る)。
シンプルに構えた位置から突いて、構えた位置に戻すだけ。
・刻み突き
・上段逆突き
・中段逆突き
・ワンツー
・刻み蹴り → 刻み蹴り
蹴りはリズム感が重要です。
蹴った足を軸足付近におろし、軸足も少し下げ距離を保ちます。
ここから2人組。
ペア相手が開脚して座ります。
相手の足を踏まないようジャンプして前進し、前に出る推進力を利用しながら深い中段突きを出す練習。
帰り道は同様に3歩バックステップして、引き込みながら裏回し蹴り。
初めてのメニューだったので悪戦苦闘してましたが、足を踏みつけることなくケガ人無しで終えました。
これもリズム感が重要です。
軽快なアップテンポの曲をかけながら練習すれば、攻撃のリズム感が芽生えるかも知れませんね。
音楽かけてるのは早練の時だけですが、ありかも知れませんね。
注意点がひとつ。
構えを崩さないこと。
前述の組手基本の中で口を酸っぱくして説明したことが、このメニューに移ってからすっかり忘れてしまっています、、
「構えを崩さずフットワークする」
「構えをくずさず蹴る」
まだまだ身体に染みついていない証拠です。
突きの前・蹴りの前に相手の攻撃をもらい失点してしまいます。
一般のEさんは自主練!
60分ひたすら形の稽古をされていました。
組手前の形の時間を加えると90分近く!
途中少しだけ合流しニーパイポでした。
とても練習熱心なEさん。
嬉しくなってきます。
どこかでガッツリ時間を取って形稽古しましょう!
2024年1月13日 (土)道場稽古84
こんにちは!
昨年行われた審査に合格し、色が変わった生徒全員に帯を手渡しました。
同じ2部の中でも、白・オレンジ・青と3色分かれるくらいにまでなってきた。
青帯の生徒が、他の生徒の模範となるような振る舞いを心がけてほしいと思います。
・稽古中の態度
・話を聞く姿勢
・目上の人に対する言葉使い
(これらは礼儀ね)
座って説明を聞く際、節度も持ち正座か胡坐で聞くようにしてください。
足を伸ばしてだらしない態度を取っていてはいけません。
(これは礼節ね)
稽古よりも先に、礼儀・礼節を大事にしていこう。
青帯の生徒には、道場を引っ張ってほしいと願っています。
多いに期待しています。
さて本日のテーマは『基本』
基本が出来て初めて応用が利きます。
土台固めをしっかり行いました。
-バンビクラス-
0・早練
1・体幹
2・固定式基本
3・移動式基本
4・組手
-モンキークラス-
5・体幹
6・固定式基本
7・移動式基本
8・組手
バンビクラス
【早練】
何やるか特に決めることなく自然発生する早練。
生徒の希望聞いたりしながら進めてます。
今日は組手基本でした。
構え方、フットワーク、刻み突き
このあとやるメニューと同じ。
数をこなして上達に繋げよう。
Sちゃんから、縄跳びのリクエスト連発で来てるので来週持っていこうかな。
【体幹トレーニング】
V字プランク・サイドプランク・プランクを行いました。
ピンと姿勢良くね。
美しい形は美しい姿勢によって生み出されます。
これから覚えていく形に繋がっていくので頑張ろう。
今日で66分でした。
【固定式基本】
スムーズに基立ちを作れるようになろう。
正面蹴りは膝を高く抱え込むことが大事です。
まだサッカーボール蹴ってる状態です。
利き足じゃない方でも抱え込めるようにね。
引き手・突き・中段横受け・上段揚げ受け・下段払い・左右正面蹴りでした。
【移動式基本】
腰に手を当て基立ちで移動します。
目的は何度移動しても『同じ長さ』『同じ幅』です。
注意点を記します。
1・前膝は軽く曲げる
2・後ろ足つま先の向きは20度
3・運足は半円を描く
4・おへそが流れない
何度も往復し追い突きまで行いました。
追い突きするタイミングは、移動足が極まりほんの少し遅れて突きを出すように。
タイミングが速いとドンっ!と音が鳴ってしまいます。
【組手】
ラスト5分フットワークと刻み突き。
少しだけですが、組手もメニューに入れています。
まずは構え方を覚えよう。
これも記しておきます。
1・身体は真横に向ける
2・顔は相手に向ける
3・膝を軽く曲げ緩い四股立ちで立つ
4・踵を指1本分浮かす
5・前拳は肘を軽く曲げ顎の高さに構える
6・奥拳は胸の前側に置く
特に大事なのが、3・5・6
どんなに動いても、膝の溜めは崩しません。
膝が伸び上がらないように。
両手の位置も崩してはいけません。
手が下がると相手の突きをもらってしまうからです。
顎の高さに前拳があると、相手の攻撃を前で捌けます。
奥拳が前拳に近い胸の前で構えることで、相手より先に突きを極めるためにそうします。
刻み突きを2挙動で指導しました。
1・前足と前拳を前方に向かって飛びこむ
2・後ろ足を素早く引きつけるとともに、1で突いた手で引き手を取る
なかなか「2」が難しいかな。
これらの組手基本を暫く続けます。
60分しか稽古時間がありませんので、集合は駆け足。
トイレはなるべく稽古前に済ませておいてね。
モンキークラス
【体幹トレーニング】
バランスディスクといつもの自重体幹でした。
バランスディスクは、片足でゆっくり沈んで一気に伸び上がって逆突き。
これは回数を競ってません。
不安定な中で、どこに重心を持っていけばバランスを保てるかインナーマッスルを刺激します。
自重の方は、久々登場のバックプランク・プランク・V字プランクで196分経過です。
【固定式基本】
本日の下半身強化は前屈立ち2連突き。
上段突きと中段突きを交互に出します。
上段突きは少しだけ身体を開き、中段突きで開いた腰を締めます。
もちろん前屈立ちを緩めてはいけません。
頭の高さを変えないことがポイントのひとつ。
これを左右行いました。
もうひとつ、斜角突き。
連突き同様に腰のキレを磨きます。
短時間ながら、下半身強化出来たんじゃないかな。
【移動式基本】
正直、これまで移動基本の量が足りていたとは言えませんでした。
素直に反省すべきところです。
しっかり基礎が出来てこその応用だと感じています。
各自、なかなか癖が抜けきれない部分があります。
当然悪い癖は形の中でも見え隠れします。
形の中で修正するよりも、基本に立ち返ってミッチリ鍛えるべきだと軌道修正です。
数をこなし身体に覚え込ます方法を取りました。
ざっと50分弱。
体育館のラインを使って意識づけ。
猫足立ちと四股立ちの幅・長さを改めて説明し、ひとつずつ丁寧に行いました。
・基立ち
・基立ち / 追い突き
・前屈立ち / 逆突き
・四股立ち
・猫足立ち / 手刀受け
ここから更に上達しようと思えば、自分の意識ひとつです。
・説明を良く聞き、
・お手本となる生徒の動きを良く見る、
・自分との違いを認識する、
・実際に試してみる
ひたすらこのループです。
思考出来る人に成長していこう。
【組手】
この時点で残り時間は45分間。
圧倒的に足りていない組手時間。
今日のメニューに形は入れていませんでした。
予定としては60分組手でしたが、既に押していました。
2組に分かれてフットワークです。
60秒間動き続ける練習です。
これを交互に3セット。
前後の出入り、左右に動いたり、緩急つけたり。
各自これまでの経験を基に自由に動きます。
組手は正解がひとつではありません。
思いおもいに動きます。
ここで重要なことは、相手を想定していること。
相手が詰めてきたら、スッとバックステップしたりといった具合に。
このあと実際に手技を使って繰り返しました。
前拳のプレス、足を上げてのフェイント。
工夫しながら自分の組手スタイルを模索していきます。
まだこんな段階ですが中にはキラっと光る技を見せてくれる生徒が居るのも事実です。
2列で向かい合い、刻み突きと中段カウンターでした。
組手競技に合わせ、刻み突きは5㎝手前まで踏み込むこと。
カウンターは道着1枚かすめるように。
刻み突きは、いかに相手をダマすか。
プレスと緩急を駆使しなければいけません。
あと距離ね。どうやって射程に入るか。
カウンター側は、相手の癖を見抜くこと。
「モーション」があればそれは、突きが来る合図見たいなものです。
待ちに徹する時(カウンター狙い)、沈むフットワークでその瞬間が来るまで感覚を研ぎ澄ませます。
行くときは迷わずドンっ!前で合わすこと。
一手遅れて差し込まれた場合は、その場に沈んで距離を保ちます。
突きは四隅の審判に長い線を見せなくては旗は上がりません。
長い突き。
肘がくの字に折れていては上がらないよ。
互いに突きは、本気の寸止めフルスピードでやってもらいます。
緊張感のある稽古をより多く重ねないとハートは鍛えられません。
笑いながらやってるとケガするので、集中力を切らさず本気で組手も取り組もう!
距離とタイミングを学び、近いうちに試合形式を取り入れていこうと思います。
※来週の稽古には必ず、特練申し込みの有無に印をつけ、今年の目標を記入して提出してください。
用紙は会員ページに添付しています。