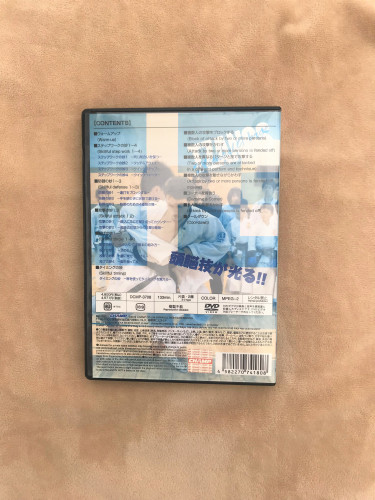ブログ
平日 夜稽古! 稽古場所のお知らせ ! その2(大池中学校)
こんにちは!
またまた新しい稽古場所となる大池中学校までのルート案内です。
8月30日(水)19:00 ~ 21:00で夜稽古しますので、ゆり生もしくは空手道にご興味をお持ちの方おられましたら、
是非お越しください。
北鈴蘭台方面方面からの道案内です。
右手に見える『谷上駅』を三田方面に通過します
左手の白い建物は『真星病院』
『出会橋』のT字路を右折です
登坂を道なりに進み、ひとつ目の信号を右折です
ほんの少し走ると右手に正門が見えてきます
正面に見える建物が体育館
体育館を囲むように駐車スペースがあります
※平日の帰宅ラッシュの時間帯に北鈴蘭台から出発しましたが、道は混んでなく約15分で到着しました。
2023年8月19日 (土)道場稽古65
こんにちは!
大会前日の最後の稽古です。
今日は訳あって、午前中多目的室で稽古となりました。
念には念を入れて前日に再度アナウンスをするべきでしたが、省略してしまい結果ご迷惑をおかけするかたちになり大変申し訳ございませんでした。
バンビクラス
1・ミット
2・固定式基本
3・形
モンキークラス
4・体幹
5・固定式基本
6・形
7・組手
-バンビクラス-
【ミット】
開始時間前にミットに興味を持つ生徒達。
「これなにーー?」
めっちゃ可愛いので、予定してませんでしたがミット蹴ることに。
一列に並んで中段回し蹴り。
コツを記しておきます。
1・基立ちで構える(前膝は軽く曲げたまま)
2・後ろ足の膝を高く抱え込む
3-1・蹴る瞬間、両手を入れ替える
3-2・蹴る瞬間、前足の踵をクルッと回す
4・足の甲をミットに弾く
5・引き足を取る(伸ばした足を腿裏にはねかえる位、膝をたたむ)
6・蹴った足を前方に下ろす
7・2歩バックステップ(この時、構えた時と向きが反対)
大事なのは1の前膝を軽く曲げたまま蹴ること、3-2の軸足の踵を回すことです。
【固定式基本】
いつもの如く立ち方から。
名前と足のカタチを覚えるまで繰り返し練習して覚えよう!
あと、基立ちと前屈立ちも追加するよ。
平行立ちをとり、引き手・突き・中段横受けです。
今日説明した、引き手と突き、横受けのポイントも記しておきます。
「引き手」
1・手首を曲げない
2・脇を開かない
3・拳はお腹より前に出ない
4・肘と拳は床と平行
「突き」
1・身体の中心を突く(正中線)
2・鳩尾の高さを突く(水月とも言う)
力むと、肩が上ずったりするので、コツは息を吐きながら突いたら上手くなるよ。
引き手も力むと、手首が曲がってしまうので、「引く」というよりも、しまうべき元の位置に戻すと言った感じが良いかもしれませんね。
「中段横受け」
1・お腹を切る
2・切った拳を肩の高さで受ける
3・肘とお腹の間は拳ひとつ分空ける
4・横受けと引き手のタイミングは同時
「奥義は基本にあり」
形は基本の組合せです。
ゆっくり丁寧に稽古していきますので、頑張って覚えてね!
【形】
明日いよいよデビュー戦を控える3人と短時間ですが、密度の濃い指導が出来たと思います。
生徒達のやる気がいつも以上にビンビンに伝わってきます!
大会申し込みから今日まで、やれることはやったことでしょう!
明日は、練習してきた形を思いっきり打つだけ!
勝っても負けても悔いが残らない様に、今の力を出し切ってほしいと思います。
全力で打て‼︎
(つづく)
-モンキークラス-
【体幹トレーニング】
今日はディスク無し。
以前のスタイルで体幹でした。
V字プランク
プランク
サイドプランク
合計139分経過しました。
姿勢にもそろそろ拘っていかなアカンな。
今度から上手に出来る子を見てもらってから体幹に入ろう。
そんな中、サイドプランクで自ら難易度を上げる生徒も居てます。
全ては自分の身体にはね返ってきます。
仲良くワイワイやりがちな道場ですが、
意識が変わり始めた生徒がいるのも事実です。
周りの変化に自分で気づける様になると
競争が激しくなるんでしょうね。
切磋琢磨してほしいな。
【固定式基本】
・重心を乗せる位置
・技のキレ
サクッと触れていざ基本に移ります。
流石2部生です。
やる気満々で返してくれます。
いつもの突き、受け、蹴りに加え、
前屈立ち / 上段突き・中段突きです。
自分に負けて前膝緩めない様に頑張ろう!
シンドいところを我慢する事で肉体と精神力が鍛えられます。
シンドくなったところからが、本当の稽古と言えるんじゃないでしょうか。
今日は全員が自分に勝ったと思います。
空手道はホントに同じことの繰り返し。
愚直に自分に嘘をつかず、やり続けて下さい。
そうすれば、いつの間にか忍耐力のある、粘り強い人になります。
ひとつの事を手を抜かず、やり続ける事が出来る人は将来社会に出た時必要とされる人材になっているはずです。
【形】
本日のテーマは技の重みについて。
生徒には、平安五段のある挙動で2種類の打ち方を観てもらいました。
どうすれば力強い技を出せるか。
ひとつ方法があって、大会前でしたが説明に少し時間を割きました。
2種類の違いは明確だった様で、一定の理解は得られてように感じています。
座学の後は、実際に自分の身体に落とし込む作業が待っています。
伝えたい内容を3つにぶった斬り、ゆっくり試し打ち。
少しずつ挙動をスムーズ繋げてもらいました。
今日指導した事が滑らかに表現出来たら、私の理想とする形に近づきます。
なんだか出来そうな生徒がいた事は収穫です。
指導していて、やり甲斐を感じる瞬間でもあります。
もちろん、この挙動だけでなく形全般に通じる事ですので、使ってみてください。
もう一つテーマがありました。
四の形で何回も言ってますが、平安二段で顕著に現れる挙動について。
形は頭の高さが上下すると美しさが損なわれます。
ではどうやって移動すれば良いかを、これも見本を披露しながら、全員で学んでもらいました。
今日指導した軸移動を、形を打つ前におさらいして練習してほしいと思います。
ガッツリ1時間、形頑張りました。
生徒が一生懸命に頑張ってくれますので、やり甲斐を感じています。
平安二段・五段・初段でした。
明日は、自分の力を出し切って!
【組手】
チューブを使って中段突きを何度も何度も。
チューブで負荷をかける事で、相手の懐へマッハの如く入る事が出来ます。
その後の稽古で実感出来たんじゃないでしょうか。
中段突きはなんと言っても相手の刻み突きを掻い潜って、カウンターを狙いますので、床スレスレ且つ長い突きを後方の副審に見せないといけません。
まだまだですが、皆んな頑張っています。
中にはオッと思わせる突きを出せる生徒もチラホラいてます。
ゆり道場も身近にお手本となる生徒が育ってきています。
良いところはマネしよう!
チューブの後は、全員横一列となりタイミング練習です。
カウンターは、相手が間合いに入って来たところを、ドンピシャのタイミングで捉えなければいけません。
カウンター狙いなので、跳ねる様なフットワークは必要ありません。
いつでもいける様に、膝を曲げ溜めを作って準備です。
突きが届く間合いに侵入してきたら踏み込むだけ。
大会前日に、タイミングを掴む練習を取り入れました。
もうひとつミットです。
ランダムに構えたミットに突き・蹴りを出す練習です。
生徒の持ち味探しながらミット構えています。
自分の得意な技で明日は大暴れしてほしいと思います。
気持ちで負けるな‼︎
平日 夜稽古! 稽古場所のお知らせ!(鵯台中学校)
いつもお世話になります!
新たな稽古場所となる、鵯台中学校までのルート案内と校内駐車場所のアナウンスです。
北鈴蘭台方面からお越しになられた場合の道案内です。
「しあわせの村」を過ぎ、カインズホーム方面に直進します。
「ひよどり台中央」の交差点を右折します
道なりに約3分程度進むと「この先行き止まり」の看板
これを左折します
左奥の緑のネットはグラウンド
さあゴール目前です
「正門」を少し超えると車両用ゲートが出て来ます
ゲートから中に入ります
校舎が3つ並んでいます
手前と中央の間にある通路に入ります(左折)
歩行者に気をつけて直進します
右折すると、砂利の駐車スペースが出て来ます
(15台駐車可能と先程連絡もらいました)
駐車スペースの前が稽古場所!
館内は大型の空調と扇風機が4台!
お手洗いも体育館の中から行き来できますので大変便利です!
2023年8月17日 (木) プレ夜練(1)@鵯台中学校
こんにちは!
5月後半から大きく体制が変わったゆり道場。
ここ暫くは平日夜の稽古場所探しに明け暮れていました。
家に居る時は、PC開いて場所探し。
気になった場所は、翌日仕事帰りに足を運んだり近くのコインパーキングを調べたり。
剣道部の人に突撃もしましたし、学校や施設に電話したことも数知れず。
正式にお断りされた学校や耐震強度の都合で見送りとなった稽古場所もありました。
そんな中、検討してくださる学校も2校ありますが、いつになるか見通しが立たない中じっと待つだけっていうのは自分の性格上、性に合いません。
夜稽古する上での条件を纏めて、候補先にそれぞれ実際に足を運んでここに決めました。
8月は唯一の空きが今日。
9月は5日.12日.19日.28日の予約が確定しました。
「初心忘るべからず」
フレッシュな気持ちで頑張ろうと思います!
今回のプレ稽古は大会直前ということもあり、少しでも勝つ確率が上がるよう形のキレを磨きました。
9月からは2時間丸ごと、形(または組手)オンリー。
あるいは、2時間かけて自由形をひとつずつ覚えていくなんてのも面白いかも知れませんね。
個人的には生徒と楽しみながら空手道を共有したいかな。
コンパス片手に神棚の向きを調べて、さあ夜稽古の開始です!
1・形
2・組手
【形】
平安二段と五段に90分時間をかけ、キレの出し方・力の伝え方を挙動ごとに稽古しました。
部分稽古で理屈を説明したので理解できたかと思います。
3人ですので、ほぼマンツーマン状態でした。
各自、細かい修正部分も指摘しています。
今日のテーマは糸東流らしく「キレ」でした。
キレとともに、技の力強さをどう表現するかも平安五段のある挙動で説明しました。
説明は割愛しますが、理屈が分かればどんな形にも応用が効きます。
いろんな形を部分練習で確認してみてはいかがでしょうか。
身体の使い方は覚えたもん勝ちです。
少人数ですので内容の濃い稽古が出来たと思います。
素晴らしい集中力を見せてくれたこともあり、充実した形稽古になりました。
20日が楽しみです!
今日のキーワードを記します。
家レンする際、振り返りしてから形稽古してほしいな。
01・準備を短く
02・拳ひとつ分の出し入れ
03・軸足でタイミングを取る
04・半円は軸足から移動する時だけ
05・上足底を使う
06・バッテン作る
07・挙動と挙動の間は、立ち方に無い立ち方を取る
08・腰を小さく緩めて素早く戻す
09・軸をブラさない(骨盤の安定)
10・上半身を前足付け根に乗せる
11・表情に気迫を込める
12・形を打つ時は主審後方の景色を見る
13・背筋の緊張感を意識する
14・挙動は大きく且つ速く
15・骨盤を前傾させる
16・力の源は下半身
【組手】
予定以上に形に時間を費やしたこと、初日なので入室前にトイレの場所や駐車スペースの確認をしていて時間が押してしまいました。
20分ちょいの時間で中段打ち込みとワンツーでした。
組手はなんといってもハートです。
当日は思い切って自分の力をぶつけてほしいと思います。
ビビッて遠慮しても相手は手加減してくれませんので60秒間、気持ちで負けないように頑張ってほしいと思います。
次回は9月5日!
10日の審査会に向け基本と形をみっちり行いたいと思います。
5日は早速1名お申込みいただきました。
駐車場も体育館もメチャクチャ広く冷房も効いていますので、快適に空手道を学べる環境だと思います。
良かったら是非来てほしいです!
タナス・フラッシュ Vol.2 -スーパースピードの防御と攻撃・突きと蹴りのテクニックロジック & 体感する世界 SAQの秘密 応用編- 2/4
こんにちは!
2012年2月12日 東京で行われたジョージ タナスセミナー応用編の第2回目をお届けします。
4・攻撃の妙
5・投げの妙
6・タイミングの妙
【攻撃の妙】
①踏込に応じて間を切ってカウンター
相手が2ステップで長い逆突きを仕掛けた場合、自分も大きくバックステップして攻撃に転じます。
相手が短い逆突きで来た場合、自分も小さくバックステップして攻撃に転じます。
要するに、逆のことすれば相手にスコアを取られてしまいますよってことです。
アジアの選手は比較的突きが短く、ヨーロッパスタイルは逆に長いようです。
3種類の刻み突きの対処です。
①前拳でパーリングしながら、小さくバックステップして中段突き
②奥拳でパーリングしながら、小さくバックステップして刻み突き
③オープンスタンスでかわしながら、サイドから奥拳で裏拳
バックステップしてから返す練習を指導されています。
タナス選手のお手本の中でこんなのが。
「相手との距離が正確に把握出来ていたら手を使わずにガード出来る」とのこと。
スウェイバックで見切って、刻み突きでポイントを取っています。
相手がフルスピードで刻み突きで攻撃してきても、間合いやリーチの長さを計算に入れているからこそ、上体だけでガードしスウェイの反動を使って刻みを飛ばしています。
動体視力が良くないと出来そうにありませんね。
(下がり過ぎると自分の技も合わなくなる)
小さい頃から空手を続けてきた小学校高学年くらいの選手なら出来そうなテクニックでした。
全ては下半身。
中段突きでもワンツーでも、距離を把握していればノーガードでかわせるとのこと。
まずバックステップで受けてかわし、反撃しますが距離が合わない場合は2本連打でも良い。
(距離が合っていれば1本ね)
勉強になります。
②超接近状態からの攻撃5種類
2012年に行われたタナスセミナー。
当時と 今とではルールも大きく異なっていて、2023年現在のルールでは密着状態が短時間続けば主審が
「分かれてー続けて」とコールし両者を離します。(続けてコールの前に攻撃すればC2、更に当ててしまえばC2 + C1)
旧ルールの中でのテクニックなので書くか迷いましたが、自分の頭の中の整理にもなるし書くことにしました。
ゼロ距離や投げにつきましては、ルールに変化があるので注意してご覧ください。
密着状態(ゼロ距離)について。
ひと昔前の空手の防御方法は、バックステップもしくは両手でガードするの2択でしたが、相手に対しダッキングで距離を詰めるテクニックが入ってきました。
ダッキングしたあと、何かをしなくてはいけません。
出来ることは2つ。
攻撃すること。
もうひとつは投げること。(小学生は禁止)
攻撃のアイデアは、
1:腕が使える状態になるまで下がって突き。
2:前手で相手の腕をつかんだまま自分の足を前後入れ替えて逆上。
3:相手の前足を刈って(体勢を崩して)突き。小学生は足払い禁止なのでスルーした方が良いですね。
4:相手道着の襟を掴み(自分の側に引っ張り)裏回し蹴り。
5:相手をほんの少し押し(空間を作り)中段回し蹴り。
【投げの妙】
①レスリングの基本の組み方
互いに向き合い、ペア相手の片腕に自分の上体を密着させ背後に周ります。
ここまではレスリングで良く観る技ですが、ここから相手の足をかけ転がせる技に応用されていました。
②足の払い方
向って組み合い、軸足を相手の足に絡めこかしています。
現ルールでは、掴みは一瞬しかダメですね。
③腰に乗せて投げる
旋回軸が腰よりも上で投げていますので割愛します。
④脚を掬って投げる
掴んでの投げは今では反則ですので割愛しますが、相手の刻み突きをダッキングしながら掬って投げる技は面白いですね。
【タイミングの妙】
①帯を使ってタイミングを覚える
中段突きのタイミングを計る良い練習方法です。
ペア相手に帯を身体の前で扇風機の羽のように、一定の速度でグルグル回してもらい帯に当たらないように中段突きする練習です。
突きのタイミングを覚えるには効果的かも知れません。
連続して突かず、しっかりと準備し試合と同じ感覚で突いています。
突きのスピードもさることながら引き手が遅いと帯が手に触れてしまいます。
タナス選手のお手本では、ワンツー・上上と2本突いています。
フルスピードで帯をグルグル回していても、手に触れることなく技を極めていて、なによりも集中力を高める練習と説明されていました。
これは良い練習です。
集中力を高める練習方法を探していたので参考にしたいと思います。
なんと!裏回し蹴りまで極めています。
余談ですが小休止を挟む時、身体が冷えないように軽く動くよう指示していました。
完全に身体を休めてはいけませんね。